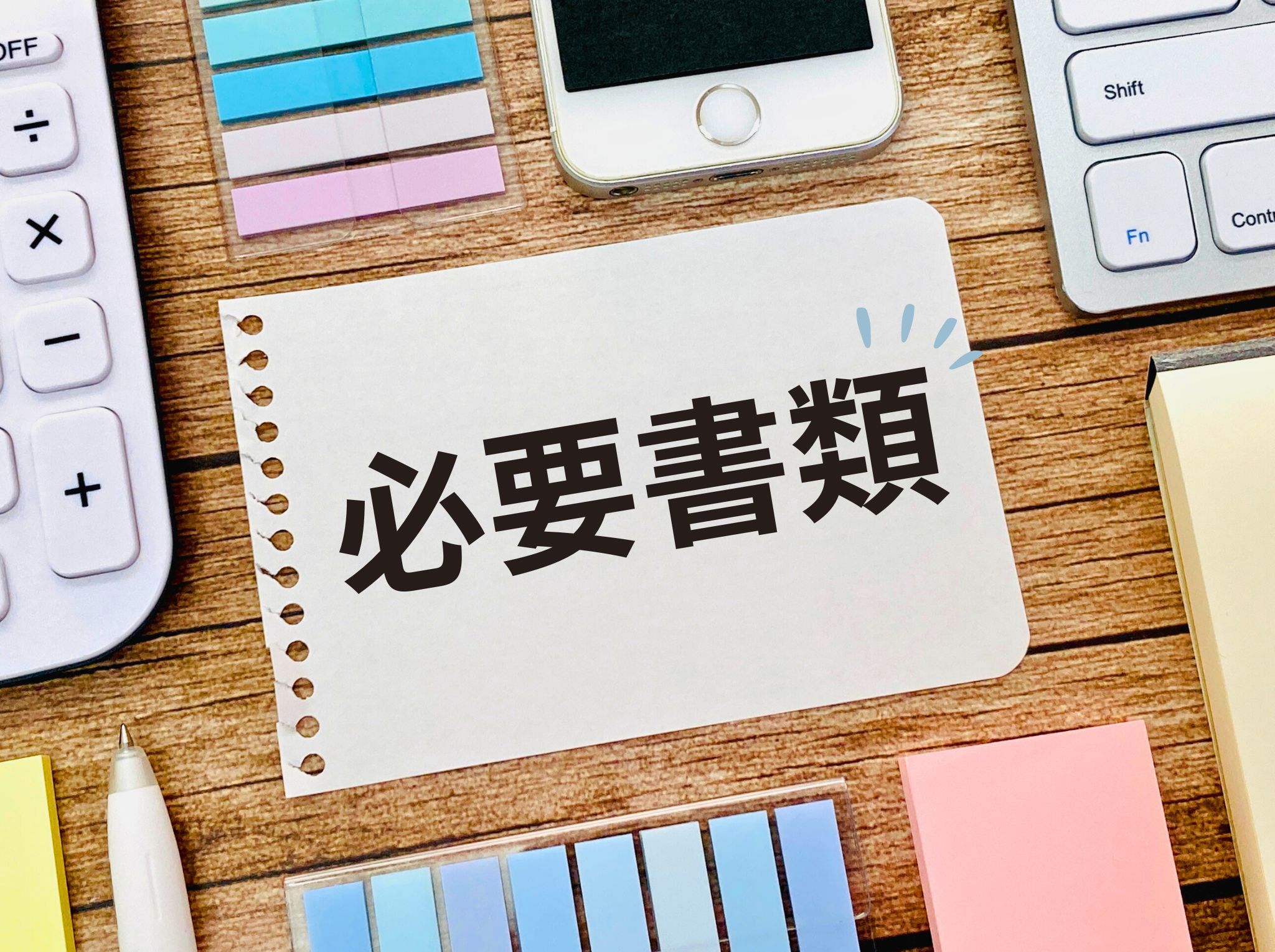危険物倉庫とは?建設する際に知っておきたい基準・法令をご紹介

最終更新日:
危険物倉庫とは?建設する際に知っておきたい基準・法令をご紹介
近年建設ニーズが高まっている危険物倉庫は、火災や爆発などのリスクを伴う危険物を安全に保管するために特別に設計された施設です。一般の物流倉庫とは異なり、危険物倉庫には「指定数量」と呼ばれる特定の数量以上の危険物を取り扱う際の厳しい基準があります。これにより、火災やその他の事故を未然に防ぎつつ、環境への影響を最小限に抑えることが求められます。
倉庫の運営にあたる企業は、危険物に関する法令や基準に基づいて、自社の倉庫の安全性を確保しなければなりません。危険物倉庫の建設時には、数多くの規制や基準をクリアする必要があり、これが面倒である一方、効果的なリスク管理のため必要不可欠です。安全な倉庫運営に向けた取り組みが求められています。
今回は、危険物倉庫を建設する際に知っておきたい基準や法令について詳しくご紹介します。
危険物倉庫とは?
本章では、危険物の定義など危険物倉庫に関する基礎知識をご紹介します。
危険物倉庫について
危険物倉庫とは、化学物質やその他危険物を安全に保管・管理するために設けられた施設のことを指します。これらの倉庫は、特に火災や爆発のリスクが高い物質を扱うため、厳格な規制と基準に従って設計・運営されなければなりません。日本では、消防法などによって危険物の取り扱いが定義されており、これらの法律に基づいて適切な管理が求められます。
倉庫を建設する際には、様々な許可申請が必要となります。これは、安全性を確保するための法的手続きを含んでおり、監視機関による厳しいチェックが行われます。危険物はその性質に応じて特別な管理が求められるため、これらの手続きは決して軽視できません。許可が認可されることで、法律に基づいた適切な運営が可能となります。危険物倉庫の設計段階から、これらの基準を遵守することで、安全で効率的な業務運営が可能となります。
危険物倉庫で保管することができる危険物
危険物倉庫で保管できる危険物としては、主にガソリンや灯油、石油製品、可燃性液体、腐食性物質、さらには一部の化学薬品が含まれます。これらの物質はその特性上、高い引火性や爆発性を持ち、取り扱いや保管には細心の注意が必要です。
消防法における危険物の定義
危険物とは、通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質のことです。 消防法では危険物を6つの類に分類・定義しています。
・第1類…酸化性固体であり、他の物質を強く酸化させる性質を持ちます。特に可燃物と混合すると激しい燃焼を引き起こす危険があります。具体的な例には、塩素酸塩類や過塩素酸塩類があります。 ・第2類…可燃性固体であり、自らが燃えやすく、低温でも引火しやすい性質を持ちます。具体的な例には、硫化りんや赤りんがあります。 ・第3類…自然発火性物質および禁水性物質が該当します。水や空気に触れることで発火したり、可燃性ガスを発生させる性質を持つため注意が必要です。具体的には、リウムやナトリウムなどがこの類に含まれます。 ・第4類…引火性液体で、燃えやすい液体全般を指します。特殊引火物やアルコール類、油類が含まれます。 ・第5類…自己反応性物質で、加熱分解によって爆発の危険がある固体や液体です。分子内に酸素を含むため、周囲の酸素がなくても燃焼が進む危険があります。具体的には、有機過酸化物やニトロ化合物が例として挙げられます。 ・第6類…第一類と同様に、他の物質の燃焼を促進する性質を持つ液体です。具体的には、過塩素酸や過酸化水素などがこの類に該当します。
これらの分類に留意し、適切な施設や設備を整えて安全対策を講じることが求められます。
危険物取扱が可能な施設の種類
危険物を取り扱うことができる施設は、大きく分けて下記の3種類あります。
1. 危険物を製造するための施設となる『製造所』 2. 大きな指定倍数で危険物を取り扱う『貯蔵所』 3. ガソリンスタンドなど、危険物を小さい指定倍数で扱う『取扱所』
この中でも危険物倉庫は2つ目の『貯蔵所』に該当します。 『貯蔵所』でも、屋内外タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所など様々な種類があります。 一般的に「危険物倉庫」と呼ばれるものは屋内の貯蔵所を指します。
「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」の違い
危険物倉庫が該当する『貯蔵所』の区分内でも、「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」では危険物の保管形態において異なる特徴を持っています。
屋内貯蔵所は、主に固体または液体の危険物を箱や棚などの容器に収納し、効率的に管理するための施設です。この施設では、分類ごとに危険物が保管され、使用する際の取扱いや安全対策に注意を払い、一定の基準に従って運営されています。
一方、屋内タンク貯蔵所は、大容量の液体危険物をタンクに直接保管する施設であり、タンクは特定の安全基準を満たすように設計されています。タンクは定期的な点検やメンテナンスが必要で、保管液の管理が求められます。そのため、液体の種類に応じた規制が設けられていて、適正な取り決めに従った運用が不可欠です。
このように、それぞれの貯蔵方法には特有の管理基準と運用ルールが存在し、場面ごとの適切な選択が求められます。
危険物倉庫建設の際に必要となる許可申請
危険物倉庫の建設にあたっては、消防署への許可申請が不可欠です。これは、指定された危険物の取扱いに関する基準を満たしているかどうかを確認するためです。具体的には、倉庫の立地や構造、保管する危険物の種類によって必要な書類が異なるため、詳細な計画を提出しなければなりません。これには、立地図面や構造設計図、危険物の種類や数量を示す資料が含まれます。
危険物倉庫建設時に知っておきたい基準
危険物倉庫建設時には、多くの規制や基準を考慮する必要があります。 本項では、建設する際に押さえておきたい基準についてご紹介します。
規模の基準について
危険物倉庫の規模については、法令に明確な基準が設けられています。 原則として、軒高は6m未満の平屋建てとされ、床面積は1,000平方メートル以下に制限されています。 この規定は、火災や爆発事故が発生した場合の被害を最小限に抑えるための重要な措置です。
第2類および第4類の危険物を扱う場合には、特定の条件を満たすことで、軒高を20m未満まで拡大することが可能です。具体的には、適切な防火設備の設置や周囲の安全対策の実施が求められます。例えば、火災発生時に迅速に対応できるよう、消火栓やスプリンクラーなどの消火設備が義務付けられています。この際も、延床面積は依然として1,000平方メートル以下に抑える必要があり、保有空地の確保も重要です。
保安距離の基準について
危険物倉庫の保安距離の基準は、万が一の事故において、火災や爆発が周辺に及ぼす影響を最小限に抑えるために規定されています。 具体的には、危険物を貯蔵する倉庫から、周囲の建物や土地に対して一定の距離を保つことが求められています。
消防法によると、例えば住居からは10メートル以上、学校などの教育機関からは30メートル以上、重要文化財からは50メートル以上の距離を保つことが義務付けられています。
また、危険物の指定数量に基づいて、保有空地を確保することも不可欠です。この保有空地は、万が一の事故や火災発生時に周囲への影響を最小限に抑える役割を果たします。 保有空地の幅は、倉庫の構造や危険物の貯蔵量により異なります。
倉庫の壁や柱、床が耐火構造の場合、指定数量の倍数によって空地の幅が変わります。
指定数量が5以下であれば0メートル、5以上10以下で1メートル以上、10以上20以下で2メートル以上という具合です。一方、耐火構造以外の場合は、基本的な空地の幅が少し広がり、指定数量5以下で0.5メートル以上が求められます。
高圧ガス等、災害を引き起こす可能性のある物質を取り扱う施設についても、特定の距離の確保が必要です。例えば、特別高圧架空電線の下での距離基準は、使用電圧によって異なり、7,000ボルトを超え35,000ボルト以下の場合は3メートル、35,000ボルトを超える場合は5メートル以上の水平距離が必要とされます。
これらの保安距離と空地の基準は、危険物倉庫から発生する可能性のある災害から人や財産を守るために不可欠なものです。建設計画において、これらの基準を遵守することは、事故の影響を軽減する重要なステップとなります。
保有空地とは
保有空地とは、危険物倉庫に関連する規制の一環として、倉庫周囲に設けるべき空間のことを指します。これは、火災やその他の事故が発生した際に、周囲に与える影響を最小限に抑えるための重要な要素です。
保有空地の面積や位置は、危険物の種類や数量、施設の規模に応じて異なるルールが定められています。この空地は、緊急時の避難経路や消火活動の妨げとならないよう設計される必要があります。
適切な保有空地を設けることで、周囲の環境への配慮や地域住民の安全性を確保することが求められます。これにより、危険物倉庫の運用がより安全に行われることになります。
構造の基準について
危険物倉庫の構造の基準については、消防法に基づき設定されています。
・屋根の構造基準 倉庫の屋根は軽量金属板等の不燃材料を使用する必要があります。これにより、火災が発生した際に延焼を防ぐ効果が期待できます。また、壁や梁についても、耐火構造であることが求められています。
・床の構造基準 床に関しても同様に、耐火構造でなければなりません。さらに、床面は水が侵入・浸透しない構造にすることが規定されています。これは、危険物が水と接触することにより反応を引き起こす可能性があるためです。必要に応じて、水を排水できるシステムを導入することも考慮されます。
・窓の構造基準 窓は網入りガラスにすることが必須です。網入りガラスは、破損しても透過性が制限されるため、火が建物外に広がるのを防ぎます。また、窓や出入り口には防火設備を設けることも義務づけられており、これは火災時の煙や炎の侵入を防ぐ重要な役割を果たします。
設備の基準について
危険物倉庫建設の際には、火災や爆発のリスクを低減させるために設備についての基準が設定されています。
・避雷設備の設置 危険物の指定数量が10倍以上の場合、避雷設備は必須です。これにより、雷の影響を受けた際に発生する可能性のある火災や爆発を未然に防ぎます。避雷設備の設置には、適切な接地システムや雷撃防止装置が含まれ、建物全体が雷の影響を受けにくくなります。
・蒸気排出設備の設置 引火点が70℃以下の危険物を扱う場面では、適切な蒸気排出設備を整えることが義務付けられています。これにより、危険物の蒸気が室内に滞留しないようにし、引火のリスクを大幅に低減させることができます。
・採光の確保 適切な明るさや採光の確保をすることで、作業者が安全に作業を行える環境を提供し、目視確認や緊急時の対応を迅速に行うことが可能になります。具体的には、作業エリアの照明は、最低でも500ルクスの明るさが必要とされることが多いため、設計段階で十分な配慮が求められます。
加えて、換気のための設備の整備も欠かせません。 これらの基準に従った設備を整えることで、危険物倉庫は安全に運用され、万が一の場合でも被害を最小限に抑えることができます
消火設備の設置基準について
危険物倉庫には、消防法に基づく消火設備の設置が求められています。消火設備は、その種類によって第1種から第5種まで分類され、それぞれ異なる設備が求められます。
第1種消火設備には、屋内外消火栓が含まれ、初期消火を担う重要な役割を果たします。 第2種消火設備にはスプリンクラー設備があり、火災が発生した際に自動的に作動し、消火活動を行います。これは特に危険物倉庫のような場所で非常に有効です。 第3種消火設備には水噴霧消火設備や泡消火設備、二酸化炭素消火設備など、異なる消火方法を持つ設備が含まれています。これにより、さまざまな火災リスクに柔軟に対応できる体制が整います。 第4種と第5種消火設備では、使用する消火器のサイズによって大型消火器と小型消火器に分かれ、それぞれのケースでの対応が必要になります。これらは物質の特性や火災の性質に応じて選定されるため、倉庫の構造や取り扱う危険物に応じた適切な選択が求められます。
消火設備の具体的な条件については、倉庫の設置状況や保管されている危険物の種類によって異なるため注意が必要です。たとえば、ある危険物倉庫では、揮発性の高い液体を扱っている場合、特別な消火設備が追加で求められることがあります。このため、詳しい仕様を把握するためには、日本消火設備装置工業会が提供している早見表を確認することが推奨されます。
危険物倉庫の設計に関わる法令・届出
危険物倉庫を設計する際には、複数の法令や規制を遵守する必要があります。まず、消防法では危険物の取り扱いや保管に関する基準が定められており、適切な許可を得ることが重要です。また、都市計画法や建築基準法も関連し、用途地域や構造的安全性が考慮されます。
港湾法は、港湾内での危険物取扱における特別な規制を設けています。さらに、各地域における政令や条例も影響するため、地域特有の要件を理解することが不可欠です。これらの法令や届出について正確に把握し、遵守することで、安全な危険物倉庫の設計が可能となります。
消防法について
消防法は、特に指定数量以上の危険物の貯蔵および取扱いの制限に重点を置いています。この法律に基づき、危険物を保管する際には指定数量を超えないよう注意が必要です。 例えば、ガソリンや石油などの液体燃料は、指定数量を超えて貯蔵する場合、その保管場所に対して厳格な基準が求められます。
消防法での具体的な規定については「危険物の規制に関する政令」に詳細が示されています。この政令は、危険物の種類ごとに求められる防火設備や保管方法を規定しており、消防法だけではカバーしきれない細かな規則が含まれています。たとえば、ガソリンの貯蔵に関しては、必ず耐圧のあるタンクで貯蔵し、周囲には防火帯を設けなければならないという具体的な基準が存在します。
消防法に準じた危険物の取り扱いは、倉庫の設計や建設時に考慮するべき重要な要素です。そのため、危険物倉庫を新設する際には、関連する法令や条例をしっかりと確認し、必要な許可を取得した上で設計を行うことが求められます。
都市計画法について
都市計画法は、土地の利用や開発に関する基本的な枠組みを定める法律で、都市や地域の適正な発展を目的としています。 危険物倉庫の建設においては、用途地域や市街地の整備方針に基づいて、危険物の製造や貯蔵に関する規制が設けられています。
例えば、都市計画法における用途地域の指定では、住居系地域、商業系地域、工業系地域などが設けられており、それぞれの地域で許可される用途が異なります。危険物倉庫は、通常工業地域や特定の区域に限定されることが多く、これに違反して建設した場合、取り壊しを命じられることもあります。このため、建設に先立って事前に地域の用途を確認し、その地域での危険物倉庫が適切かどうか判断することが求められます。
また、都市計画法は、住環境や公共交通機関の整備にも配慮した地域の発展を旨としています。危険物倉庫の設立が地域の安全や環境に与える影響を考慮し、適切な距離や保安対策を講じなければなりません。そのため、危険物の取扱いや保管については、消防法や建築基準法などと連携を取りながら、適合性を分析する必要があります。
建築基準法について
建築基準法は、建物の構造、設備、安全性、環境への影響などに関して国が定めた重要な法律です。建設物が一定の基準を満たし、安全に利用できるようにするための枠組みを提供しています。特に危険物倉庫に関連する建築基準法は、物理的な特性やリスクを考慮し、厳密な基準を設けています。
危険物を取り扱う施設においては、倉庫の設計と建設は特に慎重を要します。たとえば、危険物が漏れた場合に周囲に影響を与えないように、耐火性や耐震性に優れた材料の使用が求められます。建物の構造は耐火建築物として認定される必要があり、耐火性のある外装材や防火シャッターの設置が義務付けられています。
さらに、建築基準法では、危険物を扱う施設において従業員や利用者の安全を確保するための労働安全衛生に関する規定も含まれており、多様な認可や検査が義務付けられています。
港湾法について
港湾法は、臨港地区における土地利用や建築物の用途について重要な法律です。この法律は特に臨港地区内の土地利用に関する区分を定めており、商港区や工業区といった特定の用途地域が設定されています。これにより、港湾区域内での建設や利用が一元的に管理されるため、危険物倉庫の立地や運用に関する基準も明確になります。
港湾法の下では、建築基準法の用途地域の規定は適用されないため、特に港湾法に基づく市町村条例によって臨港地区の土地利用が管理されます。このため、例えば商港区やマリーナ港区、修景厚生港区といった特定の区域では、一般的に危険物置場の建設は認められていませんが、少量危険物庫については例外的に設置が可能です。このように、地域ごとに異なる制限が存在することから、具体的な計画を立てる際には十分な事前調査が必要です。
具体的には、大阪市では、商業や観光資源として重要な役割を果たしている地域において危険物に関連する施設の設置が厳しく制限されることが多いです。この配慮は、住民の安全や環境保護を考慮した結果であり、危険物を扱う事業者は、周辺環境に与える影響をよく理解し、適切な対策を講じる必要があります。
その他規制に関する政令や条例
危険物の規制に関する政令とは、消防法に基づいて規定されたもので、危険物の取り扱いや保管に関する詳細なルールを構築しています。これにより、特定の危険物に対する制限や、取り扱いに必要な設備の仕様などが明確にされており、特にリスクの高い物質については、厳格な基準が設けられています。
地域によっては、地方特有の火災リスクや環境条件に応じた火災予防条例が策定されており、これらの条例は市町村単位で異なります。たとえば、都市部では高層ビルが密集するため、危険物倉庫の立地や構造に特別な規制が加えられる場合があります。また、農村部では、化学肥料や農薬の保管に関する独自のルールがあり、地域住民が安全に生活するための基準が求められます。
このように、危険物規制に関する政令や地方条例は、火災を未然に防ぐだけでなく、災害発生時の被害を最小限に抑えるための重要な枠組みとなっています。具体的には、特定の危険物の保管限度を設定したり、周辺地域に対する保安距離を設けたりすることで、周囲の環境や住民に与える影響を考慮した施策が推進されています。
こうした法令や条例の理解は、危険物倉庫を設計・建設する際に非常に重要な要素となり、事業者はこれに従い適切に行動することで、事故を未然に防ぐための土台を築くことが求められています。
まとめ
危険物倉庫とは、火災や爆発のリスクを伴う危険物を安全に保管するための専門的な施設です。建設にあたっては、様々な基準や法令を遵守する必要があります。これらの基準は、事故を未然に防ぎ、地域社会や環境への影響を最小限に抑える目的で制定されています。
さらに、危険物倉庫の建設には消防法や地域の都市計画法、港湾法など、様々な規制が関わってきます。それぞれの法令に対して適切な届出や許可を取得することが、設計変更等を発生させずスムーズな建設を進める上で必要不可欠です。
なお、危険物の保管量がごくわずかであれば、一般的な冷蔵倉庫等の営業倉庫(一類倉庫)でも保管可能ですが、これは消防法で定められた「指定数量」に依存します。指定数量を超える危険物は、危険物倉庫での保管が必須です。この指定数量は、危険物の種類や性質によって異なります。また、指定数量未満の危険物であっても、市町村条例などによる規制が存在し、一律に保管できるわけではありません。たとえば、一般的には指定数量の5分の1未満であれば少量危険物として認識され、特定の手続きや資格が不要とされる場合もありますが、地域によっては異なる規制が適用されることもあります。
危険物倉庫の建設にあたっては、今回ご紹介した規制や基準を十分に理解し、適切な準備を行うことが必要です。 これにより、安全な運営が確保され、地域社会への影響を最少に抑えることが可能となります。 危険物取扱者の育成や継続的な教育も、運用の安全性向上に不可欠な要素であることを認識することが重要です。
工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1
可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。
※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
人気記事
工場・倉庫建築について
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
- これから計画を始める方
- おおよその予算やスケジュールが知りたい方
- 敷地調査や提案を希望される方