倉庫・工場の建築時には各種制限(用途地域)を確認しよう!地域によっては建築(建設)できない工場、倉庫(貸倉庫含む)に注意 | CANARIS(カナリス)
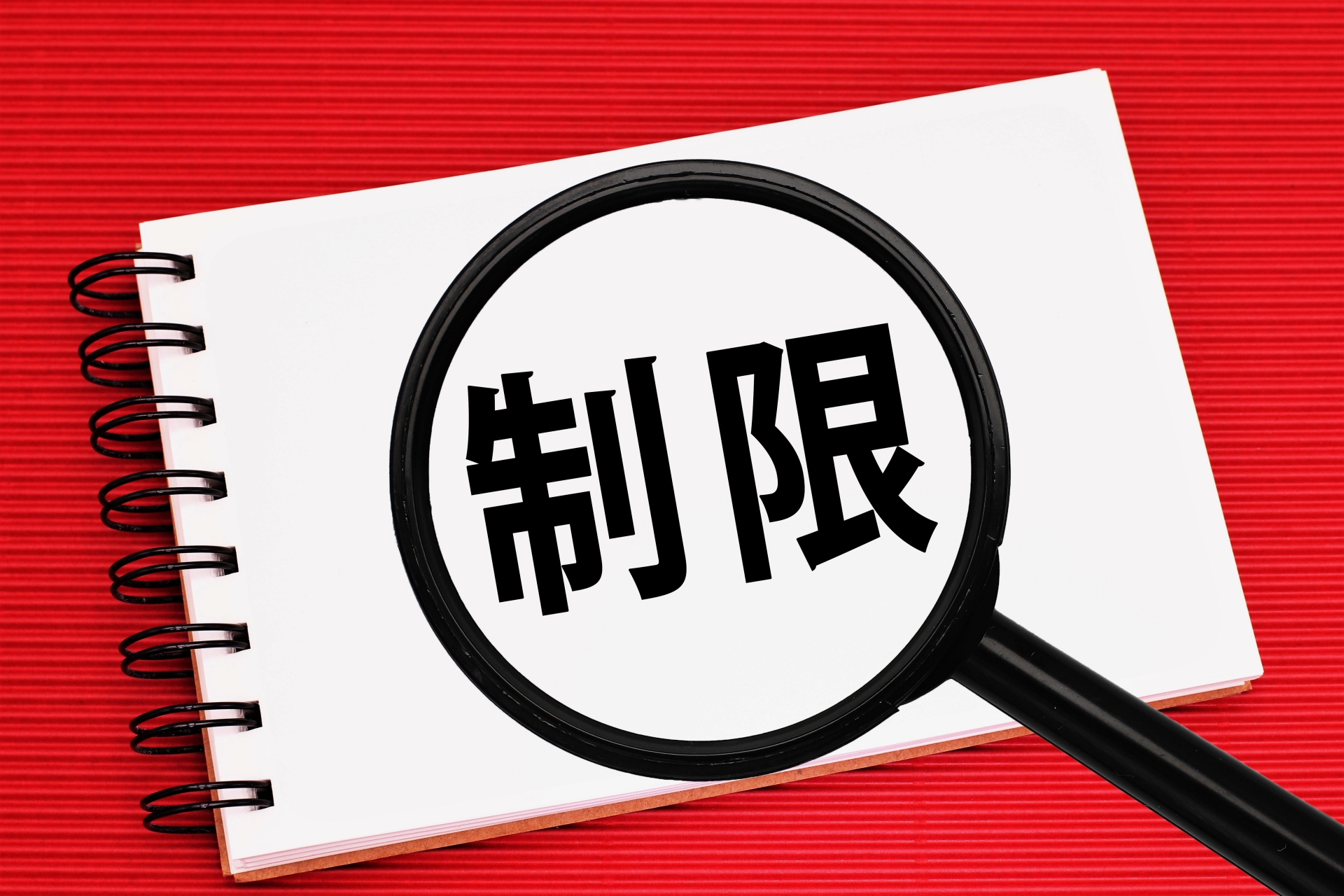
最終更新日:
倉庫や工場の建築を計画する際、建築基準法や都市計画法が定める「用途地域」などの各種制限を正しく理解することが極めて重要です。 これらの規制は、特定の土地にどのような種類や規模の建物を建てられるかを定めており、計画の初期段階での確認が不可欠です。
もし確認を怠ると、設計の大幅な変更や、最悪の場合には計画そのものが見直しとなる事態も起こり得ます。 本記事では、倉庫建築に関わる法規制の基本から、具体的な制限内容までを解説します。
建築基準法とは?
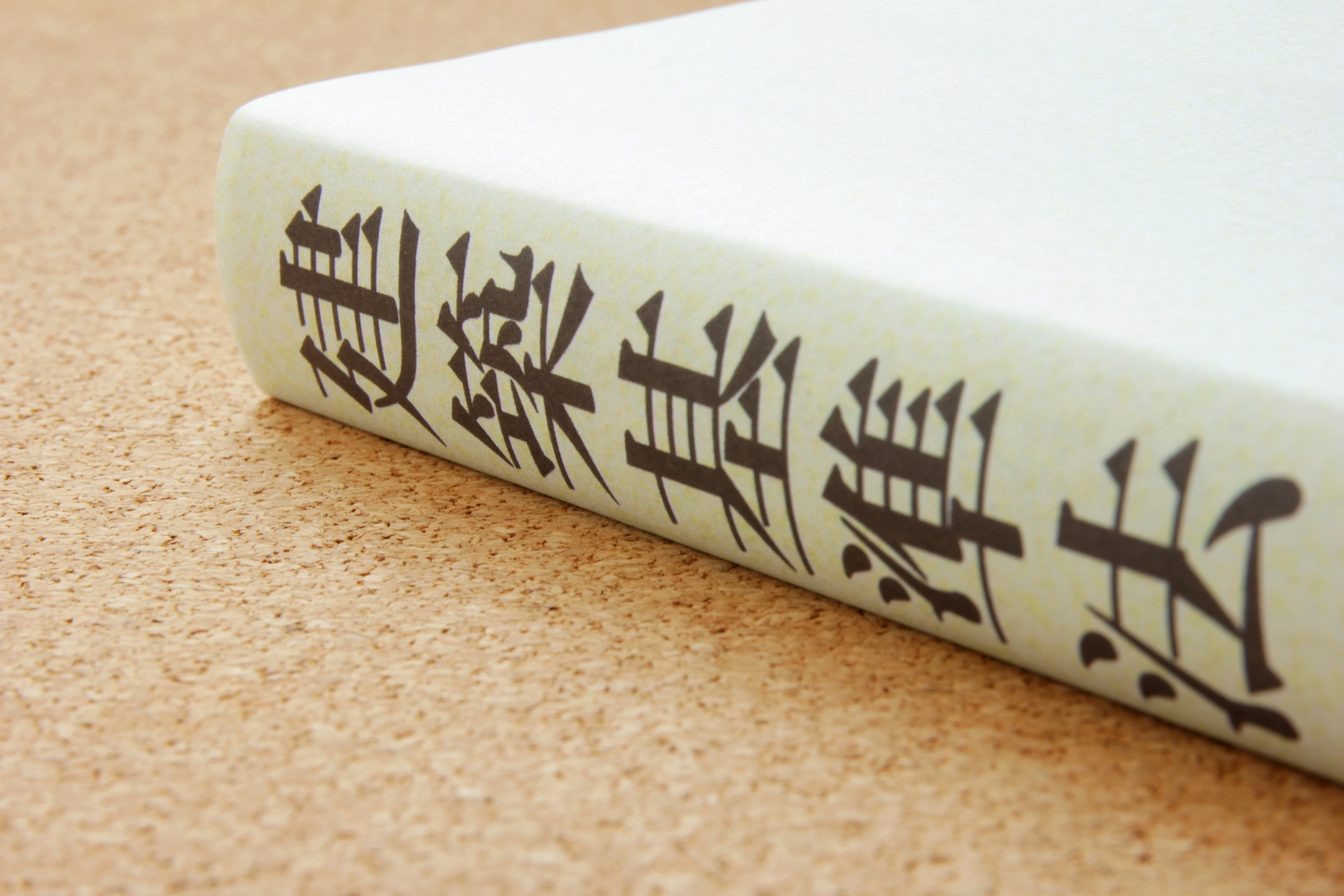
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守ることを目的に、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律です。 倉庫や工場を含むすべての建築物は、この法律に準拠して設計・建築される必要があります。
具体的には、地震や火災に対する安全性、衛生的な環境の確保、そして市街地の健全な発展を図るための様々なルールが盛り込まれています。 計画を具体化する上で、この法律の規定を遵守することが大前提となります。
建築基準法における「倉庫」の定義
建築基準法において「倉庫」とは、物品を貯蔵または保管するための施設を指し、この定義には自社の荷物を保管する自家用倉庫と、他社の荷物を預かる営業用倉庫(貸倉庫)の両方が含まれます。 法律上、倉庫は「特殊建築物」に分類されることが多く、これは不特定多数の人が利用したり、火災の危険性が高かったりする建物などを指す区分です。
特殊建築物に該当する場合、一般の建物よりも厳しい防火・避難規定や構造基準が適用されます。 また、床面積が100㎡を超える特殊建築物は、定期的な調査・検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する義務が生じるなど、維持管理においても特別な配慮が求められます。
倉庫が建築基準法を満たすには
倉庫が建築基準法に適合するためには、構造耐力、防火・避難規定、採光・換気など、多岐にわたる基準をクリアしなければなりません。 特に大規模な倉庫や危険物を保管する倉庫の場合、より厳格な安全基準が課せられます。
具体的には、積雪や地震の力に耐えうる構造計算、火災発生時の延焼を防ぐための耐火性能、そして従業員が迅速かつ安全に避難できるための通路幅や非常口の確保などが求められます。 これらの基準は、倉庫の用途、規模、建設地の地域特性によって細かく規定されており、専門家である建築士と密に連携し、設計段階で一つひとつの要件を確実に満たしていくプロセスが不可欠です。
耐火・準耐火構造
建築基準法では、火災による建物の倒壊や周辺への延焼を防ぐため、建物の規模や用途、立地する地域に応じて、耐火構造または準耐火構造とすることを義務付けています。 耐火構造とは、壁、柱、床、梁といった主要構造部が、通常の火災が終了するまでの間、倒壊せずに耐えうる性能を持つ構造のことです。
一方、準耐火構造は、一定時間、火災の拡大を抑制する性能を持つ構造を指します。 特に、市街地の中心部などに指定される防火地域や準防火地域に倉庫を建設する場合、あるいは延べ面積が大きい倉庫では、これらの構造要件が厳しく適用されます。 保管する物品の種類によっては、さらに高いレベルの防火性能が必要となることもあり、設計段階で慎重な検討が求められます。
防火区画の設置
大規模な倉庫では、万が一火災が発生した際に、炎や煙が建物全体へ一気に広がるのを防ぐ目的で「防火区画」の設置が義務付けられています。 これは、建物の内部を一定の面積ごと(一般的には1,500㎡以内)に、耐火性能を持つ壁や床、防火戸などで区画する措置です。 この防火区画によって、火災を一定の範囲に封じ込め、被害の拡大を抑制するとともに、消防隊が到着するまでの時間を稼ぎ、安全な避難経路を確保します。
区画を貫通する換気ダクトや配管部分には、熱を感知して自動で閉鎖する防火ダンパーの設置が必要です。 区画の基準は建物の面積、階数、構造によって細かく定められており、法令に適合した設計が必須となります。
内装制限
建築基準法には、火災発生時の煙や有毒ガスの発生を抑え、安全な避難を可能にするため、建物の内装に使用する材料を制限する「内装制限」という規定があります。 この規制は、特に大規模な倉庫や窓のない空間など、火災時に避難が困難になる恐れのある場所に適用されます。 対象となる壁や天井の仕上げ材には、燃えにくい性能を持つ「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」といった国土交通大臣認定の材料を使用することが義務付けられます。
この内装制限は、火災の初期段階での延焼を遅らせ、人命の安全を確保するために非常に重要な役割を担っています。 倉庫の設計においては、どの部分にどのようなレベルの内装制限が適用されるかを正確に把握し、適切な材料を選定することが求められます。
建ぺい率と容積率とは?

建ぺい率と容積率は、都市計画法に基づき、敷地に対してどれくらいの規模の建物を建築できるかを定める重要な指標です。 建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合を示し、敷地内に一定の空地を確保することで、日照や通風、防災上の安全性を高める役割があります。
一方、容積率は、敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合を定め、建物の立体的なボリュームを制限することで、人口密度やインフラへの負荷をコントロールします。 これらの率は用途地域ごとに上限が定められており、倉庫建築の基本設計に直接影響を与えます。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率は、建築面積を敷地面積で割り、100を掛けることで算出されます。 計算式は「建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100」です。 ここでいう建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積を指します。 一般的には1階部分の面積が基準となりますが、軒や庇、バルコニーなども、先端からの距離が1メートルを超える部分は建築面積に含まれます。
例えば、敷地面積が1,000平方メートルで、指定建ぺい率が60%の土地では、建築面積の上限は600平方メートルとなります。 ただし、防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地では、建ぺい率が10%加算される緩和措置があり、敷地の条件によってはより広く建物を建てることが可能です。
容積率の計算方法
容積率は建物の延べ床面積を敷地面積で割って算出します。 計算式は「容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積×100」となります。 延べ床面積は建物の各階の床面積をすべて合計した面積です。 例えば、敷地面積が1,000平方メートルで指定容積率が200%の場合、建築可能な延べ床面積の上限は2,000平方メートルです。
この上限内であれば、各階1,000平方メートルの2階建てや各階500平方メートルの4階建てといった設計が考えられます。 ただし、敷地に接する前面道路の幅員が12メートル未満の場合、その道路幅員に一定の係数(住居系地域では0.4、その他では0.6)を乗じた数値が容積率の上限となる制限もあるため、道路条件の確認も重要です。
【補足】防災備蓄倉庫は容積率が緩和される
建築基準法では、災害対策を促進するため、防災備蓄倉庫のスペースについて容積率の計算から除外できる緩和措置を設けています。 具体的には、建築物全体の延べ床面積の50分の1を上限として、防災備蓄倉庫にあたる部分の床面積を容積率算定上の延べ床面積に算入しないことが認められています。
この措置の対象となるのは、非常用の食料や飲料水、救助用資機材などを保管するための倉庫であり、その旨が設計図書に明記されている必要があります。 この緩和規定を活用することで、事業用のスペースを削ることなく、企業のBCP(事業継続計画)対策の一環として、あるいは地域貢献として防災備蓄倉庫を設置しやすくなります。 この措置は、社会全体の防災力向上を後押しする重要な制度です。
法改正が行われた背景

2019年6月に施行された建築基準法の改正には、倉庫に関する規制緩和が含まれています。 この法改正の背景には、EC市場の急速な拡大に伴う物流施設への需要増加と、既存の老朽化した倉庫の建て替えを促進するという社会的な要請がありました。 従来の法律では、特に準工業地域において、高い防火性能を持つ倉庫であっても建ぺい率の緩和措置が適用されず、敷地を有効に活用しきれないという課題が存在していました。
そこで、火災の延焼リスクが低い特定の条件を満たす平屋の倉庫については、建ぺい率の角地緩和と同様の緩和を適用することで、より効率的な土地利用と大規模な倉庫建築を可能にし、物流機能の強化と経済活動の活性化を図ることを目的としています。
法文で改正内容を確認する
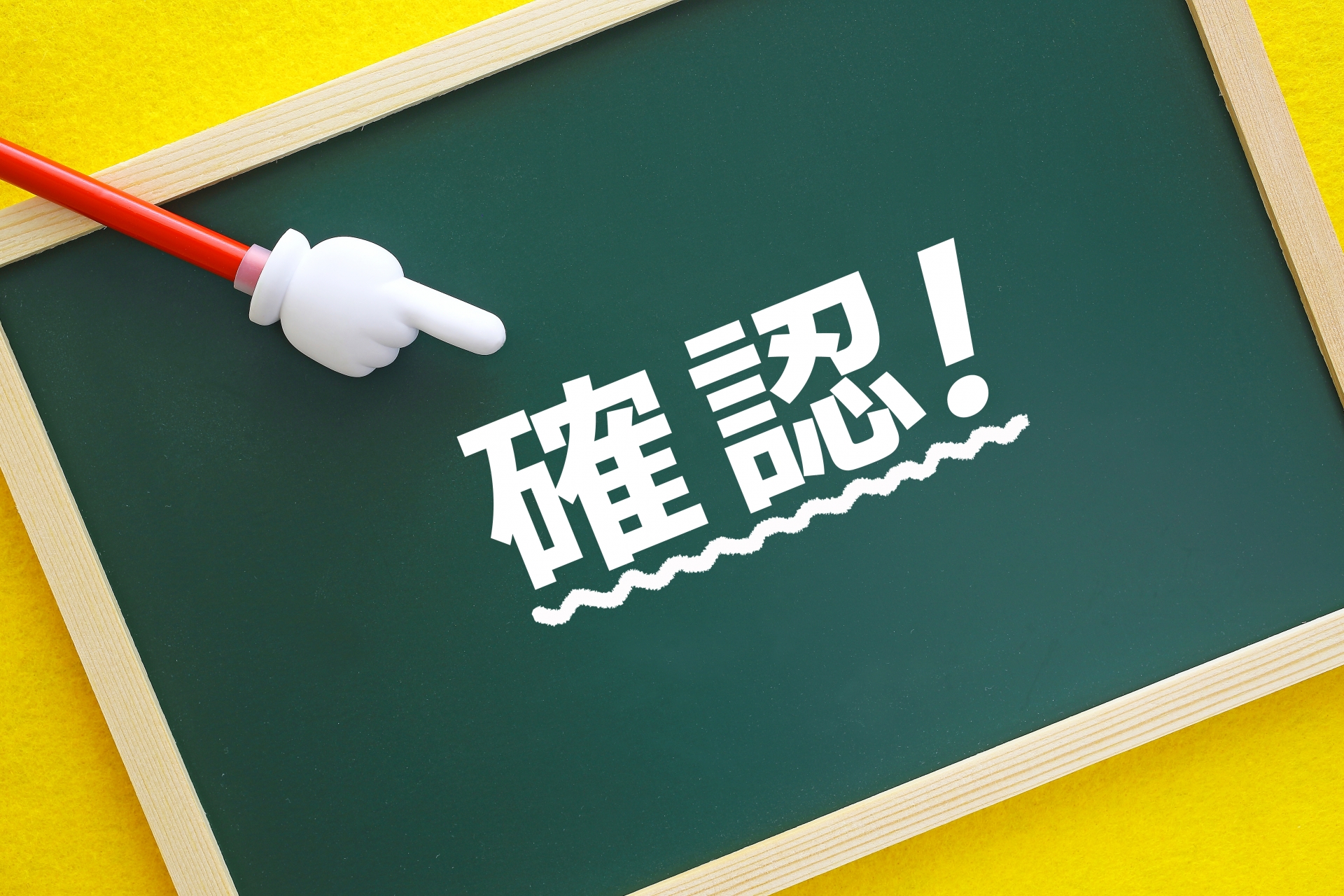
2019年に改正された建築基準法(法第53条第3項第二号)により、特定の条件を満たす倉庫について、建ぺい率が10%加算される緩和措置が導入されました。 この特例は、準工業地域内にあり、高い防火性能を持つ平屋建ての営業用倉庫が対象です。 この改正によって、これまで以上に敷地を有効活用した倉庫建築が可能になりました。
具体的には、外壁の構造や内装材、軒の面積、敷地境界線からの距離など、複数の厳しい条件が定められています。 以下で、その法文上の要件を一つずつ詳しく確認していきます。
『不燃材料』の条件について
建ぺい率緩和の適用を受けるための条件の一つに、倉庫の内装に関する規定があります。 具体的には、外壁の室内側および屋根の下面が、不燃材料で仕上げられている必要があります。 建築基準法における不燃材料とは、通常の火災による加熱が加えられても、燃焼しない、防火上有害な変形や損傷が生じない、そして避難の妨げとなる煙やガスを発生しない、という3つの性能が求められる材料です。
代表的なものとして、コンクリート、れんが、鉄鋼、ガラスなどが挙げられます。 この規定は、万が一倉庫内で火災が発生した際、建物自体が燃え広がることを防ぎ、構造体の安全性を維持することを目的としています。 設計にあたっては、指定された部位に法令で定められた不燃材料を確実に使用することが求められます。
『上階を設けない』に関する条件について
この建ぺい率緩和措置は、対象となる倉庫が「階数が一であること」すなわち平屋建てである場合に限定されています。 2階建て以上の建物は、この特例の対象外です。 この条件が設けられている理由は、建物の構造を単純化し、火災時の安全性を高めることにあります。
複数階の建物は、垂直方向への延焼リスクや、上階からの避難経路の確保といった点で、平屋建てに比べて火災時の危険性が高まります。 そのため、建ぺい率という大きな緩和を与える代わりに、建物の形状を延焼リスクの低い平屋に限定しているのです。 したがって、この緩和措置を活用して建築面積を最大化したい場合は、建築計画を平屋建てにすることが必須の条件となります。
『軒等の面積』に関する条件について
法改正による建ぺい率緩和の適用には、軒や庇の面積に関する細かい規定も存在します。 具体的には、倉庫に設けられる軒、庇、その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、5平方メートル以内でなければなりません。 この規定の目的は、建物の外周部に、火災時に延焼の足掛かりとなりうる突出部を極力設けないようにすることです。
大きな軒や庇は、隣地で発生した火災の炎や熱を受けやすく、また自らの建物から出火した際に隣地へ燃え移る原因ともなり得ます。 そのため、荷物の積み下ろしのために大きな庇を設けたいといったニーズがある場合、この緩和措置の適用は難しくなります。 設計段階で、この面積制限を遵守できるかどうかの検討が必要です。
『軒等からの敷地境界線までの距離』に関する条件について
建ぺい率緩和の適用条件として、軒や庇の先端から敷地境界線までの距離も定められています。 具体的には、軒、庇、その他これらに類するものの先端から、敷地境界線までの水平距離を1メートル以上確保することが必要です。 この規定は、隣地との間に十分な空間(離隔)を保つことで、市街地における延焼防止効果を高めることを目的としています。
万が一、隣接する建物で火災が発生した場合でも、1メートル以上の距離が確保されていれば、輻射熱による引火や火の粉による燃え移りのリスクを大幅に低減できます。 敷地を最大限に活用しようと境界線ぎりぎりに建物を配置する計画では、この条件を満たすことができないため、配置計画において十分な注意が求められます。
『建築物の用途』に関する条件について
この建ぺい率緩和措置は、全ての倉庫に適用されるわけではなく、その用途が「倉庫業を営む倉庫」に限定されている点に注意が必要です。 倉庫業法第2条第2項で定義される「倉庫業」とは、寄託、つまり顧客から依頼を受けて物品を倉庫で保管する営業を指します。
したがって、自社の製品や資材を保管するためだけの自家用倉庫は、この緩和措置の対象にはなりません。 顧客から物品を預かり保管料を得るビジネスを行う営業倉庫(貸倉庫やトランクルームなど)が対象です。 計画している倉庫が自家用なのか営業用なのかによって、この特例を適用できるかどうかが決まるため、事業計画と照らし合わせて法規制を正確に理解することが不可欠です。
【注意】あくまで緩和の対象は『建蔽率の計算』に係る部分のみ

2019年の法改正による規制緩和は、準工業地域に特定の条件を満たす営業用倉庫を建てる際の「建ぺい率」に限った措置であることを、正確に理解しておく必要があります。 この緩和によって、容積率や建物の高さ制限、道路斜線や隣地斜線といった斜線制限、あるいは防火地域に関する規定など、その他の建築基準法上の規制が変更されるわけではありません。
したがって、この特例を用いて建ぺい率が10%加算され、建築面積を広げることができても、建物の延べ床面積や高さ、隣地との関係性については、従来通りそれぞれの規制をすべて遵守しなくてはなりません。 この緩和措置を過大評価せず、一つの要素に対する特例として捉え、他の法規制と総合的に判断しながら設計を進めることが重要です。
倉庫の建築時には各種制限を確認しよう!地域によっては建築できない工場、倉庫に注意

倉庫や工場の建築を計画するにあたり、建築基準法と並んで必ず確認しなければならないのが、都市計画法で定められた「用途地域」です。 用途地域とは、都市を住宅地、商業地、工業地といった目的別に区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の種類、用途、規模を制限するルールです。
日本全国の都市計画区域は13種類の用途地域に分けられており、指定された地域によっては、そもそも倉庫や工場の建築が一切認められない場所もあります。 そのため、土地選定の最も初期の段階で、対象地がどの用途地域に指定されているかを確認することが不可欠です。
倉庫の建築制限はなんのためにある?
倉庫や工場に様々な建築制限が設けられている主たる目的は、都市全体の住環境や機能性を維持し、計画的で秩序ある街づくりを進めるためです。 例えば、閑静な住宅街に大型トラックが出入りする大規模な倉庫が建設されると、騒音、振動、交通量の増加により、住民の穏やかな生活が脅かされます。
逆に、工場のすぐ隣に住宅が建てられると、工場の操業音が住民の生活を妨げたり、住民からの苦情によって工場の操業が制約されたりする可能性があります。 こうした土地利用の混乱を避けるため、住居、商業、工業といった異なる機能を適切にゾーニングし、それぞれの地域が持つ特性を最大限に活かせるように、建築物の用途や規模に関する制限が設けられています。
用途地域とは?倉庫が建てられる場所のルール
用途地域とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成する目的で、土地をその利用目的応じて区分けしたものです。 この区分は、大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つの系統に分かれ、さらに細かく13種類の地域に分類されています。 それぞれの地域ごとに、建築できる建物の種類、用途、建ぺい率、容積率、高さなどが詳細に定められています。
倉庫の建築を考える場合、この用途地域の指定が、計画の可否そのものを決定づける最も重要な要素です。 例えば、第一種低層住居専用地域では原則として店舗や事務所すら建てられず、倉庫の建築は不可能です。 土地を取得、あるいは賃借する際には、まずその場所の用途地域を確認することが全ての始まりとなります。
【倉庫の種類別】自家用倉庫と営業用倉庫の違い
倉庫は、その利用目的によって「自家用倉庫」と「営業用倉庫」に大別され、建築基準法上の扱いや建築可能な用途地域が異なる場合があります。 自家用倉庫とは、製造業者が自社製品を保管したり、小売業者が販売商品をストックしたりするなど、企業が自らの事業のために使用する倉庫を指します。
一方、営業用倉庫は、他人の物品を預かり、保管サービスを提供することで対価を得る、いわゆる貸倉庫やトランクルーム事業などのための倉庫です。 建築制限においては、一部の用途地域で、自家用倉庫は小規模なものであれば許可されても、不特定多数の利用や広域からの車両の出入りが想定される営業用倉庫は許可されないといった違いがあります。 計画中の倉庫がどちらに該当するのかを明確にすることが重要です。
【用途地域別】倉庫が建築できるかどうかの基準
倉庫が建築できるかどうかは、用途地域によって明確に線引きされています。 13種類ある用途地域は、その特性から「住居系」「商業系」「工業系」の3つのグループに大別でき、それぞれ倉庫建築に関するルールが大きく異なります。
一般的に、住環境の保護を優先する住居系の地域では倉庫建築への制約が最も厳しく、工業活動を主目的とする工業系の地域では規制が緩やかになります。 土地を選定し、具体的な建設計画を進めるためには、これらの用途地域ごとの特性と規制内容を正確に把握することが絶対条件です。
住居系の用途地域
住居系の用途地域は、良好な住環境を守ることを最優先としており、倉庫の建築には厳しい制限が設けられています。 特に、第一種・第二種低層住居専用地域や田園住居地域では、住宅以外の建築が厳しく制限されており、原則として倉庫を建てることはできません。 第一種・第二種中高層住居専用地域や、第一種・第二種住居地域、準住居地域においては、一定の床面積以下で、かつ危険性がなく環境を悪化させる恐れが少ないと判断される自家用倉庫であれば建築が認められる場合があります。
しかし、営業用倉庫については基本的に建築不可とされることがほとんどです。 したがって、物流拠点としての倉庫を計画する場合、住居系の用途地域は候補地として適さないケースが大半です。
商業系の用途地域
商業系の用途地域である近隣商業地域と商業地域は、主に店舗や事務所、商業施設の立地を想定したエリアですが、倉庫の建築も一定の条件下で可能です。 これらの地域では、基本的に自家用営業用を問わず倉庫を建てることができます。 ただし、地域の主目的はあくまで商業の振興であるため、大規模な倉庫の建設計画では、大型車両の頻繁な出入りが周辺の商業活動や歩行者の安全を妨げないかといった点への配慮が求められます。
建ぺい率や容積率は比較的高めに設定されていますが、高さ制限や日影規制など他の規制も考慮しなくてはなりません。 都心部など利便性の高いエリアに多い反面、地価が高騰している傾向があり、コストと物流効率のバランスを慎重に検討する必要があります。
工業系の用途地域
工業系の用途地域は、倉庫や工場の建築に最も適したエリアです。 準工業地域、工業地域、工業専用地域の3種類があり、その全てにおいて自家用・営業用を問わず倉庫の建築が可能です。 準工業地域は、環境悪化の恐れがない軽工業の工場やサービス施設が混在する地域で、危険物を取り扱わない限り、幅広い種類の倉庫を建てられます。
工業地域は、どのような種類の工場でも建設可能で、大規模な物流センターの立地に適しています。 最も規制が緩やかな工業専用地域は、その名の通り工業のための地域であり、住宅や店舗の建築が原則禁止されているため、24時間稼働など、周辺環境への気兼ねなく操業できるという大きなメリットがあります。
用途地域の建築制限にも注目しよう
用途地域によって建築できる建物の種類が決まりますが、同時にその規模や形状を具体的に制限する様々な規定にも注意を払う必要があります。 土地のポテンシャルを最大限に引き出すためには、建ぺい率や容積率といった基本的な指標に加え、建物の高さを直接的に制限する「高さ制限」、隣地の日照を確保するための「斜線制限」や「日影規制」、そして市街地の火災安全性を高めるための「防火・準防火地域」の指定などを総合的に確認しなくてはなりません。
これらの制限は用途地域ごとに数値や条件が異なり、複雑に絡み合って最終的に建築可能な建物のボリュームを決定づけます。 容積率の上限まで床面積を確保できても、高さ制限によって希望する階数が建てられないといった事態も起こり得ます。
高さ制限(絶対高さ・斜線制限・日影規制)
倉庫を建築する際、その高さを制限する規制には主に3つの種類があります。 第一に「絶対高さ制限」で、これは第一種・第二種低層住居専用地域などで適用され、建物の高さを一律に10mまたは12m以下に制限するものです。 第二に「斜線制限」があり、これは道路や隣地の日照・通風を確保するため、境界線から一定の勾配で引かれる仮想の斜線内に建物を収めるよう求める規制です。 道路斜線、隣地斜線、北側斜線の3種類が存在します。
第三に「日影規制」で、これは冬至の日を基準として、周辺の敷地に一定時間以上の日影を落とさないように建物の高さを制限するもので、主に住居系地域で適用されます。 これらの規制は、特に多層階の倉庫を計画する場合に、建物の形状や階数に大きな影響を与えます。
防火・準防火地域による制限
都市計画では、市街地における火災の危険を防ぐ目的で「防火地域」および「準防火地域」が指定されることがあります。 これらの地域内に倉庫を建築する場合、通常よりも厳しい建物の耐火性能が求められます。 防火地域は、主に駅周辺や幹線道路沿いなど建物が密集する商業地などに指定され、原則として延べ面積が100㎡を超える建物は耐火建築物としなければなりません。
準防火地域は、防火地域の周辺に指定されることが多く、建物の規模に応じて耐火建築物または準耐火建築物とすることが要求されます。 これらの規定は、建物の構造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)や使用する建材の選定に直接影響し、建築コストの上昇要因となるため、土地選定の段階で必ず確認すべき重要な項目です。
条件によっては非常用の進入口も必要
建築基準法では、火災などの非常時に消防隊が外部から消火や救助活動を行うための経路として「非常用の進入口」の設置を義務付けています。 この規定は、原則として3階以上の建物、または特定の条件を満たす窓のない居室を持つ建物に適用されます。 倉庫の場合、3階建て以上の設計であったり、2階部分に窓のない事務所を設けたりすると、この規定の対象となる可能性が高まります。
非常用の進入口は、道路や通路に面した外壁部分に、規定されたサイズ(直径1mの円が内接できるなど)や構造を持つ開口部を、一定の間隔(10m以内)で設置する必要があります。 また、その位置を示す赤い逆三角形のマークの表示も求められます。 設計段階でこの規定を見落とすと、後から外壁を改修する必要が生じるため、計画初期からの確認が欠かせません。
倉庫の建築では事前の詳細確認が必須
倉庫の建築プロジェクトを成功に導くためには、計画の初期段階における法規制の入念な事前確認が不可欠です。 これまで述べてきたように、都市計画法の用途地域、建築基準法の建ぺい率、容積率、各種高さ制限、防火規定など、遵守すべき規制は多岐にわたります。
これらの確認を怠ったまま土地の購入や設計を進めてしまうと、後に希望する規模の倉庫が建てられないことが判明したり、設計の大幅な変更や許認可手続きの遅延が生じたりして、工期やコストに深刻な影響を及ぼすリスクがあります。 土地選定の段階から、自治体の都市計画担当部署への問い合わせや、建築士などの専門家と連携し、法的な制約を一つひとつクリアできるか詳細に検討することが、事業計画の確実性を高める上で絶対に必要なプロセスです。
よくある質問

倉庫の建築を具体的に検討する過程では、用途地域や法規制に関して多くの実務的な疑問が生じるものです。 例えば、検討中の土地の規制内容をどうやって調べればよいのか、万が一規制に違反してしまった場合にどのようなペナルティがあるのか、あるいは既存の建物を倉庫として利用する場合にどのような手続きが必要になるのか、といった点です。
ここでは、そうした倉庫建築にまつわる法規制に関する、よくある質問とその回答をまとめました。 具体的な計画を進める上での一助としてください。
自分の土地の用途地域を調べるにはどうすればよいですか?
所有している、あるいは購入を検討中の土地の用途地域を調べるには、いくつかの方法があります。 最も確実なのは、その土地が所在する市区町村の役所(都市計画課や建築指導課など)の窓口で直接確認する方法です。 窓口では都市計画図を閲覧できるだけでなく、担当者から詳細な説明を受けることも可能です。
近年では、多くの自治体が公式ウェブサイト上で都市計画情報(用途地域マップなど)を公開しており、インターネットを利用して手軽に調べることもできます。 「(自治体名)都市計画情報」や「(自治体名)用途地域」といったキーワードで検索すると、該当ページにアクセスできることが多いです。 これらの方法で、用途地域の種類に加え、建ぺい率や容積率の上限値なども確認できます。
用途地域に違反して倉庫を建てた場合、どうなりますか?
用途地域やその他の建築基準法に違反して倉庫を建築した場合、厳しい行政処分が下されます。 まず、建築確認申請の段階で不許可となり、工事に着手できません。 万が一、無許可で工事を進めたり、虚偽の申請で許可を得たりしたことが発覚した場合、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)から工事の停止命令や、建物の是正命令(一部または全部の除却、移転、改築など)が出されます。
これらの命令に従わない場合は、罰金や懲役といった刑事罰の対象となることもあります。 さらに、法令に違反した「違反建築物」は、金融機関からの融資が受けられなくなったり、将来的な売却が極めて困難になったりするなど、資産価値の面でも重大な不利益を被ります。 法令遵守は事業の絶対条件です。
既存の建物を倉庫に用途変更する場合も制限はありますか?
既存の建物を倉庫に用途変更する場合も、新築時と同様に建築基準法や用途地域の制限を受けます。 まず大前提として、変更後の用途である「倉庫」が、その土地の用途地域で許可されている必要があります。 例えば、元々事務所だった建物を倉庫にする場合、その地域で倉庫の建築が認められていなければ、用途変更自体が不可能です。
また、用途変更によって建物が「特殊建築物」に該当し、かつその用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は、建築確認申請の手続きが必要となります。 その際には、現行の建築基準法(耐震基準や防火規定など)に適合させることが求められるため、大規模な改修工事が必要になるケースも少なくありません。 安易な用途変更は法違反につながるため、必ず事前に専門家や行政に相談してください。
まとめ
倉庫や工場の建築計画において、建築基準法や都市計画法に定められた用途地域をはじめとする各種制限の確認は、事業の成否を左右する極めて重要なプロセスです。 用途地域の指定によって、建築できる建物の種類や規模が根本的に異なり、土地選定の段階でこの確認を怠ると計画そのものが頓挫しかねません。
また、建ぺい率、容積率、高さ制限、防火規定など、遵守すべき規制は多岐にわたり、それぞれが複雑に関係しています。 法改正による規制緩和も存在するものの、その適用条件は限定的であり、正確な知識が不可欠です。 これらの複雑な法規制を適切にクリアし、事業計画を円滑に進めるためには、自治体の担当部署への確認はもちろん、建築士をはじめとする専門家の知見を積極的に活用することが求められます。
工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1
可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。
※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
人気記事
工場・倉庫建築について
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
- これから計画を始める方
- おおよその予算やスケジュールが知りたい方
- 敷地調査や提案を希望される方





