倉庫の耐用年数や建物の減価償却について解説!

最終更新日:
倉庫を所有または取得を検討する企業にとって、耐用年数と減価償却の理解は、適切な資産管理と税務戦略の基礎となります。 これらの会計・税務上の知識は、倉庫という重要な資産の価値を正しく把握し、長期的な経営計画を立てる上で不可欠です。
本記事では、倉庫の法定耐用年数の種類や確認方法、減価償却の仕組み、さらには建物の寿命を延ばすメンテナンスのポイントから、耐用年数経過後の活用法までを網羅的に解説します。
倉庫の耐用年数の基本を理解する

倉庫の耐用年数には、税法上の基準である法定耐用年数のほか、経済的な価値を持つ期間を示す経済的耐用年数、物理的に使用可能な期間を指す物理的耐用年数の3種類が存在します。 これらはそれぞれ異なる概念であり、減価償却の計算や不動産評価、修繕計画の策定など、目的によって使い分けられます。
これらの違いを正しく理解することが、倉庫という資産を適切に管理・運用するための第一歩となります。
法定耐用年数とは
法定耐用年数とは、税法において定められている資産の使用可能な見積もり期間のことです。 減価償却費を計算する際の基準として用いられ、資産の種類や構造、用途によって詳細に分類されています。
この年数は、実際の建物の寿命や使用可能な期間を示すものではなく、あくまで税務会計上のルールに基づいた形式的な年数です。 したがって、法定耐用年数が経過したからといって、その倉庫が物理的に使用できなくなるわけではありません。 企業会計において、倉庫の取得費用を規則的に費用計上していくための重要な指標となります。
倉庫の構造・用途別の法定耐用年数
倉庫の法定耐用年数は、その構造と用途によって定められています。 例えば、国税庁が公表している耐用年数表によると、「倉庫業用」の建物として、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の場合は47年、骨格材の肉厚が4mmを超える鉄骨造の場合は34年、木造の場合は26年と定められています。
このように、建物を構成する主たる材料によって年数が大きく異なります。 自社が所有する倉庫、あるいは取得を検討している倉庫がどの区分に該当するかを正確に把握することが、減価償却計算の出発点となります。
法定耐用年数の確認方法
倉庫の法定耐用年数を確認する最も確実な方法は、国税庁のウェブサイトで公開されている「耐用年数表」を参照することです。 この表は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表として定められており、建物、建物附属設備、構築物など、資産の種類ごとに詳細な年数が記載されています。
倉庫の場合は、建物の項目から構造と用途に合致するものを探します。 もし、どの区分に該当するか判断が難しい場合や、特殊な構造の倉庫である場合には、顧問税理士などの専門家に相談して確認することが推奨されます。
中古倉庫の耐用年数の計算方法
中古倉庫を取得した場合の耐用年数は、新品とは異なる計算方法を用います。 一般的には「簡便法」という計算式が使われ、法定耐用年数を全て経過している場合は「法定耐用年数×20%」で算出します。
一方、法定耐用年数の一部を経過している場合は、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」という計算式で求めます。 例えば、法定耐用年数34年の鉄骨造倉庫を築10年で購入した場合、(34年-10年)+10年×20%=26年が耐用年数となります。 この計算により、中古資産の実態に合わせた減価償却が可能になります。
経済的耐用年数とは
経済的耐用年数とは、ある資産が経済的に見て有効に収益を生み出し続けることができる期間を指します。 これは税法上の法定耐用年数とは異なり、建物の物理的な状態だけでなく、立地条件、周辺環境の変化、市場の需要、陳腐化の度合いといった多様な要因を考慮して判断されます。
不動産鑑定評価においては、この経済的耐用年数が重視され、資産の収益性や市場価値を測るための重要な指標として用いられます。 適切な修繕や改修を行うことで、経済的耐用年数を延ばすことも可能です。
物理的耐用年数とは
物理的耐用年数とは、建物が構造的に安全性を保ち、物理的に使用し続けることが可能な期間、すなわち建物の「寿命」そのものを指します。 この年数は、建物の構造、使用されている建材の品質、施工精度、そして竣工後の維持管理(メンテナンス)の状況によって大きく左右されます。
法定耐用年数があくまで税務上の形式的な年数であるのに対し、物理的耐用年数は建物の実態に基づいています。 適切なメンテナンスを定期的に行うことで、法定耐用年数よりも大幅に長く建物を使い続けることが一般的です。
物理的耐用年数の確認方法
物理的耐用年数を正確に把握するためには、建築士や専門の調査会社による建物診断(インスペクション)を実施するのが最も有効な方法です。 専門家が建物の基礎や柱、梁といった構造躯体の劣化状況、外壁のひび割れや雨漏りの有無、設備の老朽化などを詳細に調査し、総合的に判断します。
また、建物の設計図書や過去の修繕履歴、定期点検の記録なども、物理的耐用年数を推定する上で重要な情報源となります。 これらの情報をもとに、今後必要となる修繕箇所やその時期を予測し、長期的な修繕計画を立てることができます。
減価償却について知っておこう
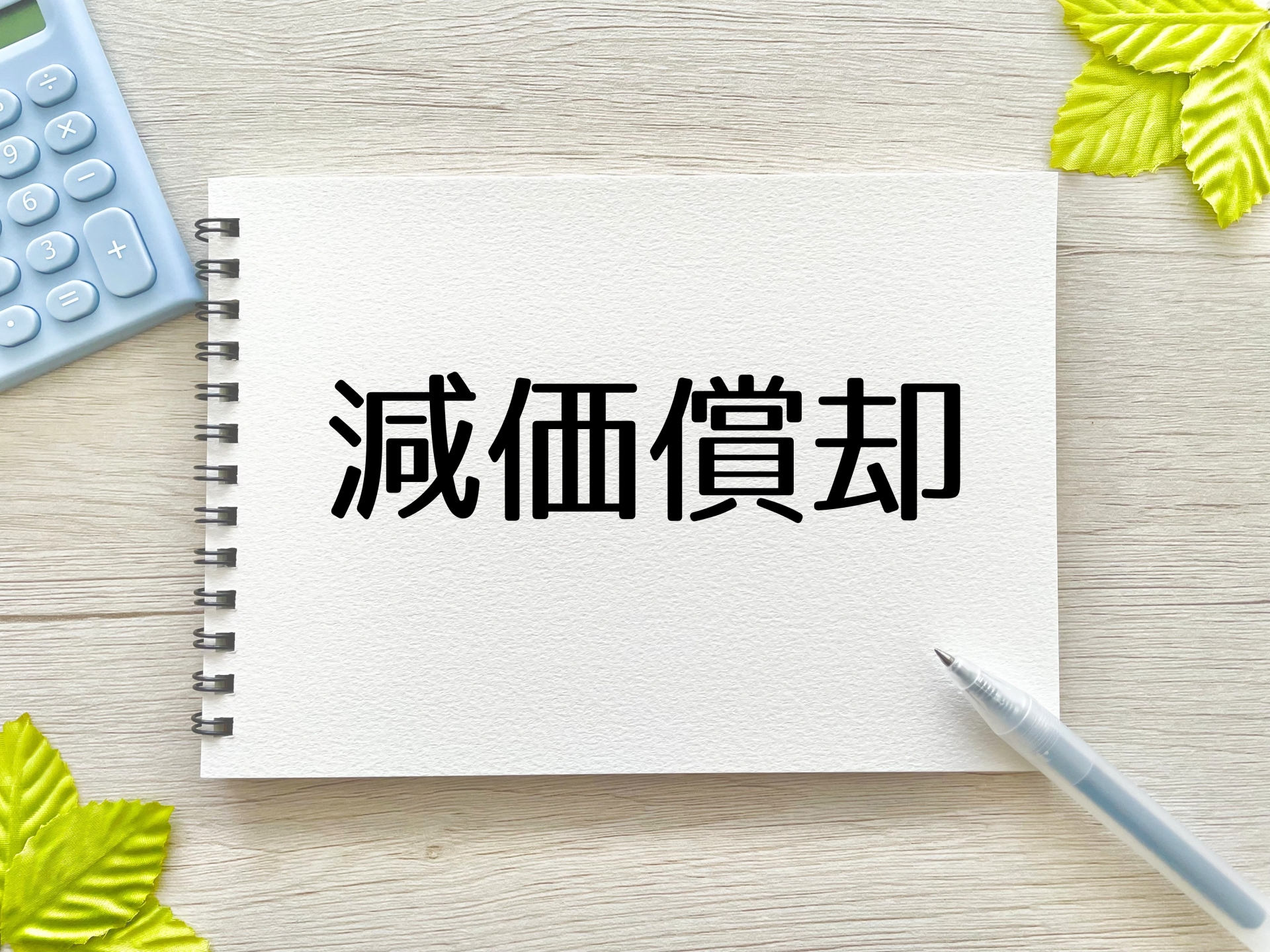
減価償却は、倉庫などの固定資産の取得にかかった費用を、その資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって分割し、毎年の経費として計上する会計上の手続きです。 時間の経過や使用によって資産の価値は減少するという考えに基づいています。
この処理により、企業の損益をより正確に把握できるだけでなく、減価償却費として計上した金額分だけ課税所得が減少し、結果として法人税などの節税につながります。 主な計算方法には、毎年同額を償却する「定額法」と、初期に多く償却する「定率法」があります。
減価償却の基本的な仕組み
減価償却は、高額な固定資産の取得費用を、購入した年に一度に経費として計上するのではなく、定められた耐用年数にわたって分割して費用化する会計処理です。 資産は使用することで徐々に価値が減少していくという考え方に基づいています。 毎年の決算で、この価値の減少分を「減価償却費」として費用計上します。
これにより、資産の取得という大きな支出が単年度の損益に与える影響を平準化し、企業の財政状態や経営成績をより実態に即して示すことができます。 また、この処理は税額計算にも影響を与えます。
定額法とは
定額法は、減価償却の計算方法の一つで、毎年一定額の減価償却費を計上する方式です。 計算がシンプルで分かりやすいため、将来の費用予測が立てやすいという特徴があります。 この方法では、固定資産の取得価額に、耐用年数に応じて定められた償却率を乗じて毎年の減価償却費を算出します。 資産を使用している期間中、その価値が均等に減少していくという考えに基づいています。
現在の税法では、建物や建物附属設備、構築物といった資産については、原則としてこの定額法を用いて減価償却計算を行うこととされています。
定額法の計算方法と計算例
定額法による減価償却費は、「取得価額×定額法の償却率」という計算式で算出されます。 償却率は、資産の法定耐用年数に応じて定められています。 例えば、取得価額が7,000万円で、法定耐用年数が34年の鉄骨造倉庫(倉庫業用)を例に考えてみましょう。
耐用年数34年の場合の定額法の償却率は0.030です。 したがって、年間の減価償却費は「7,000万円×0.030=210万円」となります。 この場合、原則として毎年210万円を、耐用年数が尽きるまで費用として計上し続けることになります。
定率法とは
定率法は減価償却の計算方法の一つで未償却残高(取得価額から過去の減価償却費累計額を差し引いた金額)に一定の償却率を乗じて減価償却費を算出する方法です。 この方法の特徴は資産の取得初期に減価償却費が最も多く計上され年数が経つにつれてその額が減少していく点にあります。
初年度の費用計上額が大きくなるため早期に投資を回収したい場合や導入初期の利益を圧縮したい場合に有利に働くことがあります。 ただし現在の税法では建物や建物附属設備には適用できず主に機械装置や器具備品などで選択可能な方法です。
定率法の計算方法と計算例
定率法の減価償却費は、「未償却残高×定率法の償却率」で計算します。 ただし、この計算で算出した金額が「償却保証額(取得価額×保証率)」を下回った年からは、計算方法が変わり、「改定取得価額×改定償却率」で毎年同額を償却します。
例えば、取得価額500万円、耐用年数8年の機械装置の場合、定率法の償却率は0.250です。 初年度の減価償却費は「500万円×0.250=125万円」となります。 2年目は、未償却残高である375万円(500万円-125万円)に0.250を乗じて、93万7,500円が減価償却費となります。
建物の減価償却と倉庫の関連性
倉庫は税法上「建物」に分類されるため、減価償却の対象となる資産です。 企業が倉庫を建設または購入した場合、その取得にかかった費用は、取得した事業年度に一括で経費にすることはできません。
代わりに、その倉庫の構造や用途に応じた法定耐用年数に基づき、減価償却という手続きを通じて、毎年の費用として分割計上していく必要があります。 この会計処理は、企業の正確な損益計算を行う上で不可欠であり、法人税額の算定にも直接影響を与えるため、会計および税務上の重要な実務となります。
減価償却が節税につながる仕組み
減価償却費は会計上は費用として計上されますが、実際に現金が社外へ流出するわけではない非資金費用という特徴があります。 この減価償却費を損金として計上することで、企業の利益、すなわち課税対象となる所得金額を圧縮することができます。 課税所得が減少すれば、その金額に税率を乗じて計算される法人税や事業税、住民税などの納税額が結果的に減少します。
このように、減価償却を適切に行うことは、企業のキャッシュフローを改善し、手元資金を確保することにつながる有効な節税策となります。
倉庫の耐用年数を延ばすためのポイント

倉庫の資産価値を長期にわたって維持し、安全に利用し続けるためには、法定耐用年数とは別に、物理的な寿命を延ばすための取り組みが重要です。 具体的には、建物の定期的なメンテナンスや専門家による点検が不可欠となります。 これらを計画的に実施することで、大規模な修繕が必要となる事態を未然に防ぎ、結果的にライフサイクルコストの削減にもつながります。
また、建物本体だけでなく、庫内で使用する棚やマテハン機器などの設備を適切に管理することも、倉庫全体の機能を維持する上で欠かせません。
建物のメンテナンス方法
倉庫の物理的寿命を延ばすためには、計画的なメンテナンスが不可欠です。 特に、建物を雨風から守る屋根や外壁は劣化しやすいため、定期的な点検と補修が重要となります。 雨漏りや外壁のひび割れは、構造体である鉄骨の錆や腐食を招き、建物の強度を著しく低下させる原因です。
また、定期的な塗装の塗り替えは、美観を保つだけでなく、防水性能を回復させ、建材を紫外線から保護する効果もあります。 排水溝の清掃を怠ると雨水が溜まり、漏水や建物の基礎部分への悪影響を及ぼすため、こまめな確認が必要です。
寿命を延ばすための点検の重要性
建物の寿命を延ばすには、日常的な目視点検に加え、専門家による定期的な建物診断が極めて重要です。 専門家は、普段見えない部分や専門知識がなければ判断できない構造体の劣化、設備の不具合などを早期に発見できます。 点検結果に基づき、長期的な視点での修繕計画を策定することで、突発的な大規模修繕による多額の出費を避け、計画的な予算管理が可能になります。
法律で定められた点検だけでなく、企業が自主的に詳細な点検を行うことが、倉庫の資産価値と安全性を長期にわたり維持することに直結します。
棚や設備の適切な管理
倉庫の機能を維持し、耐用年数を延ばすためには、建物本体だけでなく、内部の棚や設備の管理も同様に重要です。 重量物を保管するラックは、定期的にボルトの緩みや部材の変形がないかを確認し、損傷があれば速やかに補修または交換する必要があります。
また、フォークリフトなどのマテリアルハンドリング機器も、定期的なメンテナンスを怠ると故障のリスクが高まり、作業効率の低下や重大な事故につながる可能性があります。 これらの設備を適切に管理し、計画的に更新していくことが、安全で効率的な倉庫運営の基盤となります。
耐用年数が過ぎた倉庫の新たな活用法

税務上の法定耐用年数が経過した倉庫であっても、資産としての価値が完全になくなるわけではありません。 物理的に使用可能な状態であれば、その建物の状態や立地条件に応じて、さまざまな形で活用する道が残されています。 自社の事業で使用し続ける以外にも、第三者への売却や貸出によって収益化を図ったり、リノベーションによって新たな価値を付加して再利用したりするなど、複数の選択肢が考えられます。
企業の経営戦略や市場の動向を踏まえ、最適な活用法を検討することが重要です。
売却のケース
法定耐用年数を経過した倉庫でも、建物がまだ使用できる状態であれば、中古物件として売却できる可能性があります。 買主にとっては、減価償却による節税メリットは小さくなりますが、新築に比べて初期投資を大幅に抑えられるという利点があります。
特に、交通の便が良いなど立地条件に恵まれている場合は、土地の価値が評価され、建物付きの不動産としてスムーズに売却先が見つかることも少なくありません。 売却価格は建物の劣化状況や市場の需要によって変動するため、複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な価格を見極めることが肝心です。
貸出の可能性
自社で利用しなくなった倉庫は、他の企業に賃貸することで安定した収益源とすることができます。 EC市場の拡大に伴い、物流拠点としての倉庫需要は依然として高く、立地や規模によっては有利な条件での貸出が期待できます。
また、通常の倉庫としての賃貸だけでなく、建物の特性を活かしてトランクルームや撮影スタジオ、イベントスペースなどに用途を変更して貸し出すという選択肢もあります。 ただし、貸出にあたっては、借主のニーズに合わせて一定の改修や修繕が必要になる場合があるため、投資コストと見込まれる賃料収入のバランスを慎重に検討する必要があります。
再利用や建て替えの方法
耐用年数が過ぎた倉庫を、自社で引き続き活用する方法として、大規模なリノベーションによる再利用や、建て替えが挙げられます。 リノベーションでは、断熱性能の向上や設備の刷新、オフィスの併設などを行い、より付加価値の高い施設へと生まれ変わらせることが可能です。
一方、建物の老朽化が著しい場合や、現在の事業内容に建物の仕様が合わなくなった場合には、一度解体して最新の設備を備えた倉庫に建て替えることも有効な選択肢です。 建て替えには高額なコストを要しますが、保管効率や作業効率が大幅に向上し、長期的な視点での投資対効果が期待できます。
倉庫耐用年数や減価償却の理解は、企業の重要な役割
倉庫の耐用年数と減価償却の知識は、単なる会計処理や税務申告のためだけにとどまりません。 これらは企業の資産管理と経営戦略に深く関わる重要な要素です。 税務上のルールである法定耐用年数と、建物の実態である物理的寿命の違いを認識し、計画的なメンテナンスを通じて資産価値を維持することが求められます。 また、減価償却の仕組みを正しく運用することで、節税を通じて企業のキャッシュフローを健全化させることができます。
倉庫という資産を長期的な視点でいかに管理し、活用していくかを計画的に考えることが、持続的な企業経営の基盤を支えます。
工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1
可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。
※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
人気記事
工場・倉庫建築について
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
- これから計画を始める方
- おおよその予算やスケジュールが知りたい方
- 敷地調査や提案を希望される方





