新築・増築・改築・移転の違いをわかりやすく解説!定義や確認申請などについても詳しくご紹介!

最終更新日:
工場や倉庫、オフィスビルの所有者にとって、建物の工事に関する「新築」「増築」「改築」「移転」という用語の違いを正確に理解することは、法令遵守やコスト管理の観点から極めて重要です。 建築基準法においてこれらは明確に区分されており、実施する工事がどの定義に当てはまるかによって、必要な確認申請の手続きや防火規制などが異なります。
本記事では、事業用物件におけるこれらの建築行為の定義と、それに伴う実務的な手続きについて解説します。
建築行為の基本を理解する
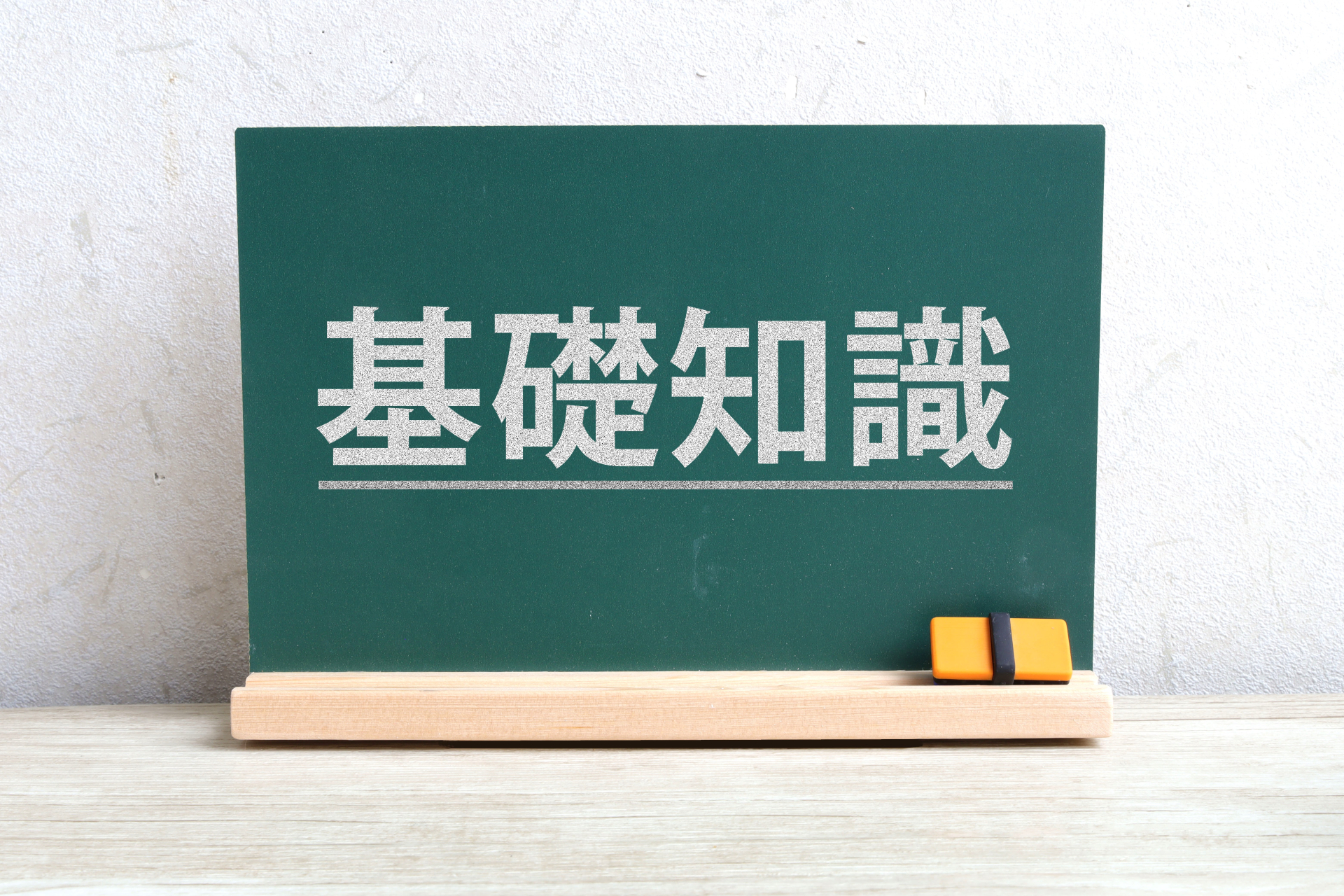
建築基準法では、建築物を建築する行為を「新築」「増築」「改築」「移転」の4つに大別しています。 これらの定義は単なる言葉の違いではなく、確認申請の要否や適用される法規制を決定づける基準となります。
特に工場や事業所では、生産ラインの拡張や設備の更新に伴う工事がどの区分に該当するかを事前に把握しておくことで、違法建築のリスクを回避し、スムーズな事業計画の遂行が可能となります。
新築とは何か
新築とは、更地になっている土地に新たに建築物を建てること、または既存の建物を取り壊して更地にした後に、以前よりも規模が大きく異なる建物を建てることを指します。
事業用地において、既存の工場とは別に、隣接する新たな敷地を取得して倉庫を建設する場合などは新築に該当します。 また、一度建物が消失した後に、用途や構造、規模が著しく異なる建物を再建する場合も新築として扱われるため、法的な要件を再確認しなければなりません。
増築とは何か
増築は、既存の建物を残したまま、同一敷地内で床面積を増加させる行為です。 平屋の倉庫を2階建てにするような縦方向の拡張や、工場の横に新たな作業スペースを継ぎ足す横方向の拡張が含まれます。
また、同じ敷地内に離れとして別の棟を建てる場合も、法的には増築として扱われます。 事業用物件では、既存施設の稼働を維持しながら拡張できる手段として採用されることが多いですが、建ぺい率や容積率の上限を超えないよう注意が必要です。
改築とは何か
改築とは、既存の建物の全部または一部を取り壊し、その位置において、用途・構造・規模が「著しく異ならない」建物を再び建てることを指します。 火災や自然災害で建物が滅失した後に、元の建物と同等のものを再建する場合も改築に含まれます。 ポイントは「従前と同様」であることです。
工場の建て替えにおいて、構造や規模を大幅に変更する場合は「新築」とみなされ、現行のより厳しい法規制が適用される可能性があります。
移転とは何か
移転とは、同一敷地内において、建物を解体せずにそのままの状態で別の位置へ動かす行為を指します。曳家とも呼ばれる手法です。
現代では、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の大型工場やビルでも曳家は技術的に可能であり、コストを抑えられる場合もあります。実際、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物の曳家事例も存在します。例えば、旧グランドプリンス赤坂旧館(鉄骨鉄筋コンクリート造)の移動工事や、横浜銀行本店(鉄筋コンクリート造)の移動工事などがあります。
プレハブ事務所や小規模な倉庫など、移動が容易な構造物で行われることもあります。なお、敷地外へ移動させる場合は、移転ではなく新築扱いとなるため注意が必要です。
改築とリフォーム(改修)の違い

一般的に「リフォーム」や「リノベーション」という言葉は広く使われていますが、これらは建築基準法上の用語ではありません。 一方で「改築」は法的に厳密に定義された建築行為です。
オフィスの内装変更や工場の設備更新を計画する際、それが単なる修繕にとどまるのか、法的な「改築」や「大規模の修繕」に該当するのかを見極めることは、建築確認申請の必要性を判断する上で不可欠です。
建築基準法上の定義の違い
建築基準法において「改築」は、建物の除去や再建を伴う行為を指します。 対して、一般的なリフォームは、壁紙の張り替えや設備の入れ替えなど、建物の構造自体には手を加えない工事を指すことが大半です。
法的には、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の一種以上に対し、過半の修繕や模様替えを行わない限り、建築確認申請を要するような建築行為とはみなされません。 用語の混同は手続きの漏れにつながるため、明確な区別が求められます。
大規模の修繕・模様替えとの関係
リフォームに近い工事でも、主要構造部の一種以上について、その過半を修繕・模様替えする場合は「大規模の修繕」または「大規模の模様替え」と定義されます。 これらは「改築」とは異なりますが、一定規模以上の特殊建築物(倉庫、工場、事務所などを含む)では、建築確認申請が必要となります。
例えば、老朽化した工場の屋根を全面的に葺き替える場合などがこれに該当し、単なるメンテナンスの枠を超えた法的手続きが発生します。
工場・倉庫・オフィスを改築する主な目的

事業用物件における改築は、単なる老朽化対策以上の戦略的な意味合いを持ちます。 耐震性能の向上によるBCP(事業継続計画)対策や、断熱性能を高めて光熱費を削減する省エネ化が主な動機です。
また、生産効率を高めるためのレイアウト変更や、最新の物流システム導入に合わせた構造変更も行われます。 企業イメージの刷新や従業員の働きやすさを向上させるために、オフィス環境を現代的に作り変えることも重要な目的の一つです。
増築のメリット

事業拡大に伴いスペースが必要になった際、移転や完全な建て替えではなく「増築」を選択することには、経営資源の有効活用という面で大きな利点があります。 既存の資産を活かしつつ、必要な機能を付加できるため、コストや時間の面で合理的な選択肢となり得ます。
ここでは、事業用物件における増築の具体的なメリットについて解説します。
延床面積の広がり
増築の最大の利点は、物理的な作業スペースや保管スペースを確保できることです。 製造業であれば新たな機械設備の導入が可能になり、物流業であれば在庫保管能力が向上します。
敷地内に未利用のスペースがあれば、土地を新たに購入することなく床面積を増やせるため、土地取得にかかる多額の費用や手間を省くことができます。 既存施設と動線を直結させることで、業務効率を損なわずに規模を拡大できる点も魅力です。
建替えよりコストがいい
全面的な建て替えと比較して、増築は工事費を大幅に抑えることが可能です。 既存建物の解体費用が不要であるか、最小限で済むためです。
また、基礎工事や躯体工事も増築部分のみに限定されるため、材料費や人件費の総額が低くなります。 浮いた予算を最新設備の導入や内装のグレードアップに回すことができるため、費用対効果の高い投資が可能となります。 予算配分の柔軟性が高い点は、経営判断において有利に働きます。
住みながら工事が出来る
工場やオフィスの場合、「業務を止めずに工事ができる」ことは極めて大きなメリットです。 建て替えの場合は仮移転が必要となり、引越し費用や仮店舗・仮工場の賃料、さらには休業による機会損失が発生します。
増築であれば、既存エリアで操業を続けながら、並行して工事を進めることが可能です。 生産ラインや物流機能を維持したまま拡張工事を行うことで、顧客への供給責任を果たしつつ、事業の成長を図ることができます。
増築にかかるデメリット
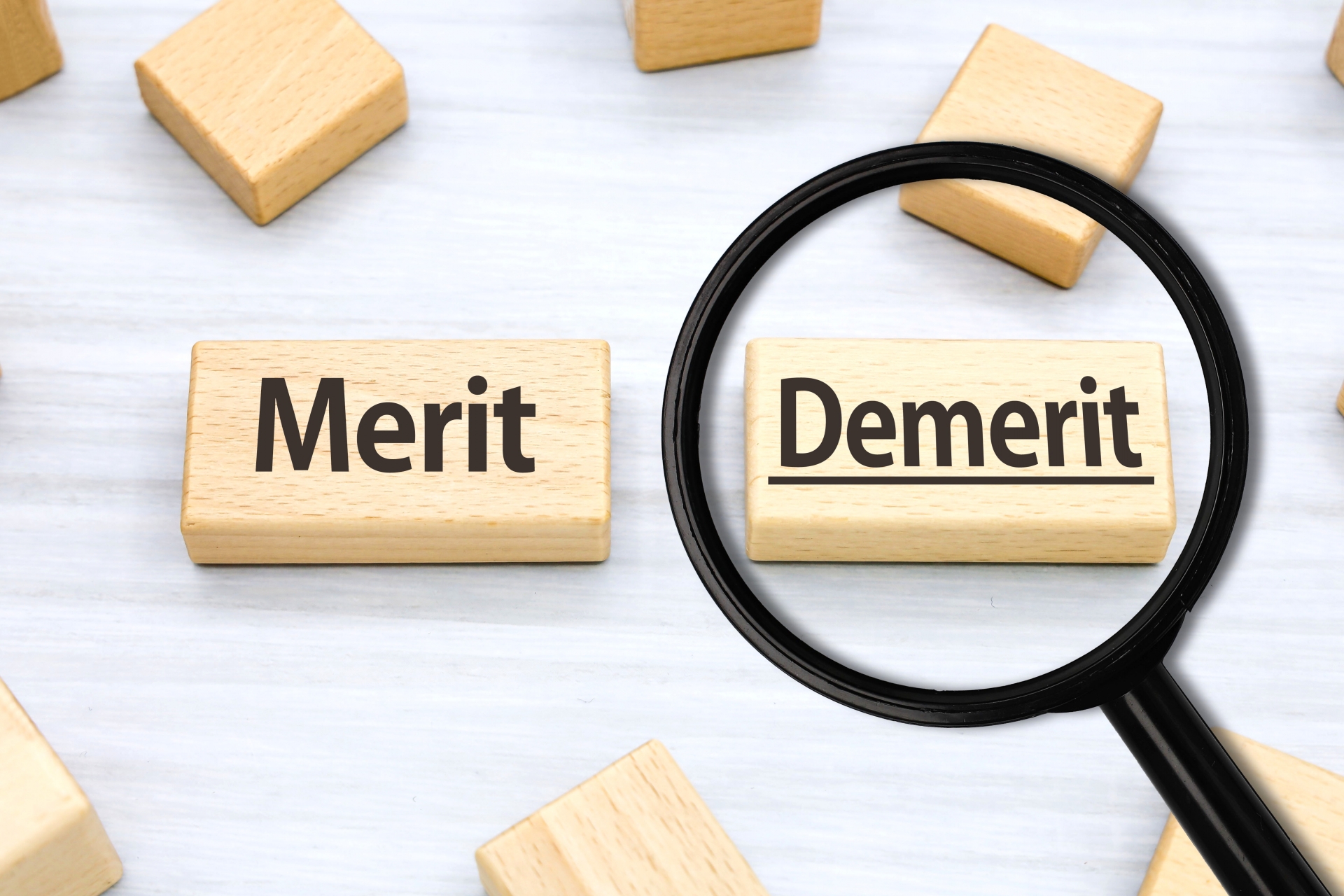
コストや稼働維持の面でメリットの多い増築ですが、既存建物と新しい建物を接続することによる弊害や法的な制約も存在します。 安易な計画は将来的な資産価値の低下や法的なトラブルを招く恐れがあります。
増築を検討する際は、構造的なリスクや行政手続きの煩雑さ、さらには税制面での負担増についても十分に考慮する必要があります。
見た目や強度の低下
増築部分は既存部分と建築時期が異なるため、外壁の色や質感に差異が生じ、建物全体の一体感が損なわれることがあります。 より深刻なのは構造面です。 地震発生時、新旧の建物は揺れ方が異なるため、接続部分(エキスパンションジョイント等)に大きな負荷がかかります。
適切な構造設計を行わないと、接合部から雨漏りが発生したり、最悪の場合は亀裂が生じたりするなど、建物の強度や耐久性に悪影響を及ぼす懸念があります。
登記や確認申請が必要
増築によって床面積が増加するため、建物表題変更登記を行う必要があります。 また、防火地域・準防火地域内での増築や、それ以外の地域でも10平方メートルを超える増築を行う場合は、建築確認申請が必須です。 これには建築士による図面作成や行政機関への手数料が発生します。
特に事業用物件は規模が大きいため、消防法などの関連法規への適合審査も厳しくなり、着工までの準備期間が長くなる傾向があります。
固定資産税の増加
建物の床面積が増えると、その分だけ固定資産税の評価額が上がります。 増築部分は新築同様の評価がなされるため、経年劣化による減価償却が進んでいる既存部分に比べ、平米あたりの税額が高くなることが一般的です。 また、大規模な改修を伴う場合は、建物全体の評価が見直される可能性もあります。
増築による事業収益の増加だけでなく、ランニングコストとして増大する税負担も事業計画に組み込む必要があります。
増築の際に発生するその他の費用
増築に伴い、電気容量や水道管の径が不足する場合は、インフラ設備の引き込み直し工事が必要となります。 また、既存建物が「既存不適格」の状態にある場合、増築を機に現行法規に合わせて既存部分へスプリンクラーや排煙設備を設置しなければならないケースがあります。
これらの付帯工事費用は当初の見積もりから漏れやすいため、事前の詳細な調査と予算計上が不可欠です。
増築の流れと注意点

工場やオフィスの増築プロジェクトを成功させるには、綿密な計画と法令チェックが欠かせません。 住宅とは異なり、労働安全衛生法や工場立地法など多岐にわたる規制が関与するためです。
初期段階から専門家を交えて既存建物の状態を調査し、法的なクリアランスを確保しながら設計を進めることが、手戻りのないスムーズな工事を実現する鍵となります。
増築計画の確認事項
最初に確認すべきは、敷地の法的条件です。 建ぺい率や容積率に余裕があるか、用途地域による制限はないかを調査します。 特に工場の場合、騒音や振動に関する規制や、危険物の貯蔵量に応じた保安距離の確保が必要になることがあります。
また、前面道路の幅員によって容積率が制限される場合もあるため、土地そのものが持つポテンシャルと制約を正確に把握することから計画は始まります。
既存建物への影響を考慮する
増築を行う際、既存建物の日当たりや通風を阻害しない配置計画が求められます。 窓が塞がれることで、既存オフィスの採光や排煙の法的基準を満たせなくなるリスクがあるためです。
また、既存建物の構造耐力が現行基準に満たない場合、増築部分と構造的に切り離して(エキスパンションジョイント等で)設計する必要があります。 無理な接続は既存建物の耐震性を低下させる要因となるため、構造設計者による慎重な検討が必要です。
快適な居住空間を考える
事業用物件において、従業員が効率的かつ安全に業務を行える環境を整備することは重要です。増築によって動線が複雑になり、作業効率が低下することは避けるべきです。新旧エリアの段差を解消し、空調効率のバランスを考慮し、部署間のコミュニケーションを妨げないレイアウトが求められます。
また、将来的な増員を考慮し、トイレや休憩室などの厚生施設を合わせて拡張・改修することは、従業員の満足度維持に繋がります。
増築が難しいケース

すべての物件で自由に増築ができるわけではありません。 土地の条件や法規制によっては、物理的なスペースがあっても増築が許可されない、あるいは莫大なコストがかかるために現実的ではないケースが存在します。
計画の初期段階で以下の阻害要因がないかを確認し、場合によっては移転や建て替えへの方針転換を検討する必要があります。
法令上の制限
すでに敷地ごとの許容容積率や建ぺい率を使い切っている場合、それ以上の床面積の増加は認められません。 また、市街化調整区域などの特殊なエリアでは、原則として新たな建築行為が制限されています。 さらに、高度地区や日影規制などの高さ制限により、上階への積み増しができないこともあります。
法令は改正されることがあるため、建設当時は適法でも、現在の基準では増築不可となるケースも少なくありません。
再建築不可物件の場合
建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接していない「接道義務違反」の土地では、原則として建築確認申請を伴う増築は認められません。 これを「再建築不可物件」と呼びます。 事業所が路地奥に位置する場合などは注意が必要です。
ただし、接道条件を改善するために隣地を買い取ったり、特定行政庁の許可を得たりすることで可能になる例外もありますが、基本的には大規模な改修は困難となります。
改築を行う際の建築基準法上の注意点

改築工事は、既存の権利関係や法規制が複雑に絡み合うため、新築以上に慎重な法適合確認が求められます。 特に建築基準法は人命保護を目的としているため、構造強度や防火性能に関する審査は厳格です。
事業用建物においては、用途や規模によって手続きの難易度が大きく変わるため、関連する条項を正しく理解し、適切なプロセスを踏む必要があります。
建築確認申請が必要となる条件
改築において建築確認申請が必要となるのは、主に以下のケースです。 第一に、防火地域準防火地域内での工事であれば、面積にかかわらず申請が必要です。 第二に、それ以外の地域であっても、床面積が10平方メートルを超える改築を行う場合。
第三に、工場や倉庫、事務所などの「特殊建築物」で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超える大規模な修繕模様替えを行う場合です。 これらを怠ると違法建築となります。
用途変更を伴う場合の手続き
建物の使い道を変えることを「用途変更」と呼びます。 例えば、空き倉庫を工場に改修する場合や、オフィスビルを物品販売店舗に変える場合などが該当します。 この用途変更する部分の床面積が200平方メートルを超える場合、建築確認申請が必要です。
用途が変われば求められる耐火性能や避難経路の基準も変わるため、単なる内装工事だけでなく、法的な安全基準を満たすための改修工事が必須となります。
既存不適格建築物の扱い
建設当時は適法だったものの、その後の法改正により現行基準を満たさなくなった建物を「既存不適格建築物」と呼びます。 この建物を増築や改築する場合、原則として建物全体を現行の法規に適合させる必要があります(遡及適用)。
ただし、一定の条件下では緩和措置が適用され、増築部分のみの適合で済む場合もあります。 既存不適格の解消には多額の費用がかかることが多いため、事前のコスト試算が重要です。
建築基準法以外で確認すべき関連法規

事業用物件の改築では、建築基準法以外にも遵守すべき法律が多数存在します。 消防法では、建物の構造や用途に応じた消火設備や警報設備の設置が義務付けられています。 工場立地法では、特定工場の敷地内における緑地面積の割合(緑地率)が定められています。
また、各自治体の条例により、景観への配慮やバリアフリー化が求められることもあります。 これらを総合的にクリアしなければ、工事の許可は下りません。
まとめ
事業用物件における新築・増築・改築・移転はそれぞれ建築基準法で明確に定義されており、選択する手法によってコスト、工期、法的手続きが大きく異なります。 特に既存不適格建築物の扱いや用途変更の要件は複雑であり、専門的な判断が不可欠です。
事業の発展に合わせて最適な施設環境を整えるためには、初期段階から建築士や行政書士などの専門家と連携し、法令を遵守した確実な計画を立案することが成功への近道となります。
よくある質問

工場や倉庫、オフィスの改修を検討されている方から寄せられる、よくある質問をまとめました。 用語の定義や法的な義務についての疑問を解消し、適切な改築・増築計画にお役立てください。
改築とリフォームの違いは何ですか?
「改築」は建築基準法上の用語で、建物を一度取り壊して同等のものを再建する行為を指します。 一方「リフォーム」は法的な定義はなく、一般的に内装の変更や設備の修繕などを指します。
確認申請の要否に関わるため、区別が必要です。
改築をする際に建築確認申請は必要ですか?
原則として必要です。 特に防火地域・準防火地域内での工事や、それ以外の地域で10平方メートルを超える場合、または200平方メートルを超える特殊建築物の大規模な修繕を行う場合は必須となります。
改築を行うと固定資産税は上がりますか?
建物の価値が上がるとみなされた場合、固定資産税は上がります。 特に増築による床面積の増加や、主要構造部の改築により建物の耐用年数が延びるような工事を行った場合は、評価額が見直される可能性が高いです。
既存不適格の建物でも増改築は可能ですか?
可能ですが、原則として建物全体を現行の法令に適合させる必要があります。 ただし、条件によっては緩和措置があり、増築部分のみの適合で許可される場合もあります。
専門家による詳細な調査が必要です。
業務を稼働させたまま工事を行うことはできますか?
増築や部分的な改築であれば、工事区画を明確に分けることで稼働しながらの工事が可能です。 ただし、騒音・振動対策や、工事車両と業務車両の動線分離など、十分な安全管理計画が必要となります。
倉庫から工場へ変更する場合も改築にあたりますか?
建物を壊して建て直さない場合は、建築基準法上の「改築」には該当せず「用途変更」に当たります。ただし、変更する床面積が200平方メートルを超える場合は建築確認申請が必要となり、工場の基準に合わせた内装や設備の改修工事が求められます。
工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1
可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。
※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
人気記事
工場・倉庫建築について
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
- これから計画を始める方
- おおよその予算やスケジュールが知りたい方
- 敷地調査や提案を希望される方





