建築確認申請書とは?確認済証や検査済証との違い、申請の流れ、トラブル対処法を解説
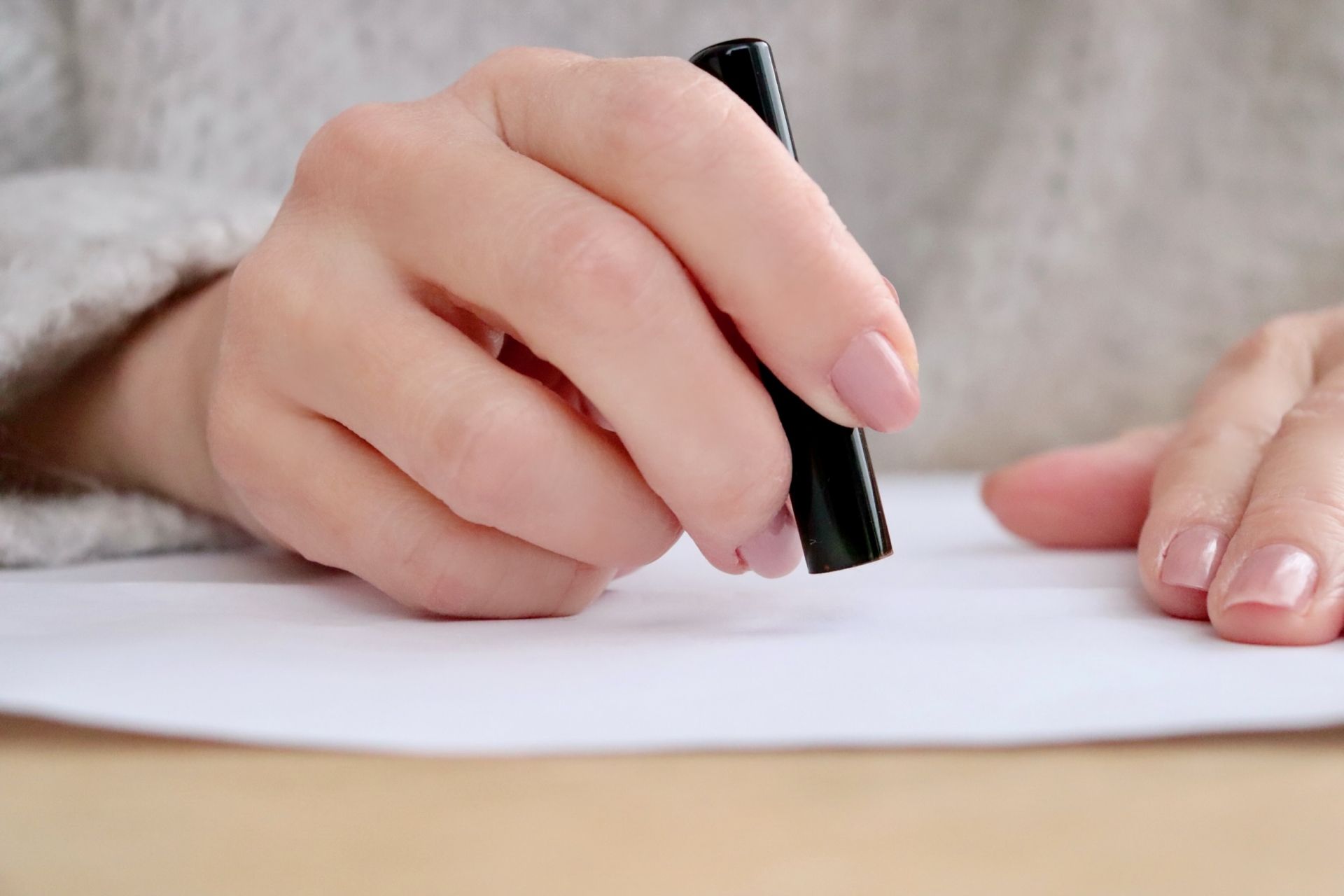
最終更新日:
建築確認申請書とは、建物を新築・増築する際に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかを行政や指定確認検査機関に確認してもらうために提出する書類です。ここでは、建築確認申請書の役割や、混同しやすい建築確認済証・検査済証との違い、申請の流れ、そして申請に関する注意点やトラブル対処法について、わかりやすく解説します。建物を建てる際に必要となる基本的な知識として、しっかりチェックしておきましょう。
建築確認申請とは

建築確認申請とは、建物を建てる際にその計画が建築基準法や関連法令に適合しているかを行政や指定確認検査機関に確認してもらうための手続きを指します。この手続きを通じて、建築物の安全性や適法性がチェックされます。建築確認申請は、建物を建てる上で非常に重要なプロセスであり、この申請がなければ工事を始めることができません。ここでは、建築確認申請の役割や、どのようなケースで必要になるのかをわかりやすく解説し、建物を建てる前にぜひチェックしておきたいポイントをご紹介します。
建築確認申請書の役割
建築確認申請書の役割は、これから建てようとする建物の計画が、建築基準法や都市計画法などの関連法規に適合しているかを公的に証明することにあります。この申請書を提出することで、行政や指定確認検査機関による審査が行われ、建築物の安全性や適法性が確認されます。建築確認申請書は、単なる手続き上の書類ではなく、建築プロジェクトが法律に基づき適切に進められていることを示す重要な書類であり、建築主や工事関係者が共通認識を持つための基準ともなります。建築計画を具体的に進める上で、この申請書の役割を正しく理解しておくことは、スムーズなプロジェクト遂行のために不可欠な知識と言えるでしょう。
建築確認が必要となるケース
建築確認が必要となるのは、主に以下のようなケースです。まず、建物を新築する場合、原則として全ての建物が建築確認の対象となります。また、既存の建物を増築したり改築したりする場合でも、その規模や内容によっては建築確認が必要となることがあります。例えば、増築によって床面積が10平方メートルを超える場合や、主要構造部にあたる壁や柱などを変更する大規模なリフォームを行う場合などが該当します。さらに、用途を変更する場合も建築確認が必要となることがあります。例えば、事務所として使用していた建物を工場として使用する場合など、建物の用途を大きく変更する際には、新たな用途での安全性や適法性を確認する必要があるためです。ただし、防火地域および準防火地域外で増築面積が10平方メートル以内である場合など、一部例外的に建築確認が不要となるケースも存在します。建物の計画を進める際には、建築士などの専門家と相談し、自身のケースが建築確認の対象となるかどうかを事前にしっかりとチェックすることが重要です。
建築確認済証と検査済証の違い

建築確認済証と検査済証は、どちらも建物の建築に関わる重要な書類ですが、それぞれ異なるタイミングと目的で発行されます。これらの書類の違いをわかりやすく理解しておくことは、建築プロセスを円滑に進める上で非常に重要です。ここでは、それぞれの書類がどのようなものか、そしてなぜこれらの書類が必要となるのかを解説し、建築を進める上でチェックすべきポイントを明らかにします。
建築確認済証とは
建築確認済証とは、提出された建築確認申請書の内容が、建築基準法や関連法令に適合していると認められた場合に交付される書類です。この確認済証は、工事を着工しても問題がないことを証明するものであり、これがないと原則として建築工事を始めることができません。つまり、建築確認済証は、建築計画そのものが法的に問題ないという「お墨付き」のようなものと言えるでしょう。建築主は、この確認済証を受け取ってから工事を開始することになります。建築確認済証の交付を受けるためには、建築確認申請に必要な様々な図面や書類を揃え、提出する必要があります。
検査済証とは
検査済証とは、建築工事が完了した後、その建物が建築確認済証の内容通りに建てられているか、そして建築基準法などの法令に適合しているかを確認するための完了検査に合格した場合に交付される書類です。つまり、検査済証は、実際に建てられた建物が適法であることを証明する書類です。この検査済証がないと、原則としてその建物を合法的に使用することができません。特に、建物を売却したり、増築や大規模なリフォームを行ったりする際には、この検査済証の提示を求められることが多くあります。検査済証の交付を受けるためには、工事完了後に完了検査を申請し、検査に合格する必要があります。
書類が必要となる理由
建築確認済証と検査済証が必要となる理由は、建築物が建築基準法をはじめとする各種法令に適合し、安全かつ適法に建てられていることを公的に証明するためです。建築確認済証は、工事を始める前に計画段階での適法性を確認することで、法令違反の建設計画によるトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。一方、検査済証は、工事が完了した後に実際に建てられた建物が、申請通りの内容で、かつ法令に適合していることを確認することで、建物の安全性を担保し、将来的な紛争を防ぐために必要となります。これらの必要書類があることによって、建築物の質が一定以上に保たれ、そこで生活あるいは活動する人々の安全と健康が守られるのです。また、これらの書類は、建物の履歴情報としても機能し、将来的な増改築や売却、あるいは行政手続きの際に、その建物の適法性を示す重要な証拠となります。確認済証と検査済証は、どちらも建物のライフサイクルにおいて不可欠な書類と言えるでしょう。
建築確認申請の流れ

建築確認申請は、建物を建てるプロセスにおいて特定のタイミングで行われます。まず、建物の基本的なプランが固まり、設計図などの必要な書類が準備できた段階で、建築主またはその代理人(通常は建築士)が建築確認申請書を提出します。これは、工事の着工前に行う必要がある手続きです。申請先は、建築地の特定行政庁(市区町村など)または指定確認検査機関となります。申請書が提出されると、建築基準法などに適合しているかの審査が行われ、問題がなければ建築確認済証が交付されます。この確認済証が交付されて初めて、工事を着工することができます。したがって、建築確認申請は、設計が完了し、いよいよ建築工事に取り掛かる直前のタイミングで行われる、工事着工のための非常に重要な手続きと言えます。
建築確認申請に必要な書類
建築確認申請を行う際には、様々な種類の必要書類を提出する必要があります。これらの提出書類は、申請する建物の規模や構造、用途などによって異なりますが、一般的には以下のような図書やファイルの内容が含まれます。まず、建築確認申請書そのものが必須となります。これには、建築主の情報や建物の概要、工事の内容などを記載します。次に、建築地の敷地に関する書類として、敷地求積図や地盤調査報告書などが必要となる場合があります。建物の計画に関する詳細を示す図書としては、配置図、平面図、立面図、断面図、構造計算書、設備図などがあります。これらの図面には、建物の間取りや構造、使用する材料、設備の配置などが詳細に記載されます。また、防火避難に関する図書や、省エネルギー基準への適合性を示す書類なども必要に応じて提出します。さらに、申請手数料の支払い証明や、建築主の委任状なども添付書類として求められることがあります。これらの書類は、建築基準法などの法令に適合しているかを審査するために不可欠であり、それぞれの内容に不備がないように正確に作成する必要があります。書類作成には専門的な知識が必要となるため、通常は建築士がこれらの必要書類を取りまとめ、提出します。
建築確認申請に関する注意点

建築確認申請を進める際には、いくつかの注意点があります。まず、申請が不要となる特定のケースが存在することを理解しておくことが重要です。また、申請後に計画に変更が生じた場合の取り扱いについても事前にチェックしておく必要があります。これらの点を把握しておくことで、スムーズな申請手続きを行い、後々のトラブルを避けることができます。
申請が不要なケース
建築確認申請は原則としてほとんどの建築行為で必要となりますが、例外的に申請が不要となるケースも存在します。例えば、防火地域および準防火地域以外の区域で、床面積の合計が10平方メートル以内の増築や改築を行う場合は、建築確認が不要とされています。また、ごく小規模な物置やカーポートなど、一定の基準を満たす簡易な構造物についても、建築確認の対象とならない場合があります。さらに、国や地方公共団体が行う建築行為の一部についても、特例として建築確認が不要とされることがあります。ただし、これらの例外規定は複雑であり、地域によって条例が異なる場合もあります。自身の計画が申請不要なケースに該当するかどうかを自己判断するのではなく、必ず事前に建築地の特定行政庁や建築士などの専門家に確認することが重要です。安易に判断して申請を怠ると、後々法令違反となる可能性もあるため、慎重な対応が必要です。
申請後の計画変更
建築確認申請を行い、建築確認済証の交付を受けた後に、建築計画に変更が生じる場合があります。計画の変更が生じた場合は、原則として再度「計画変更確認申請」を行い、改めて行政または指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。軽微な変更、例えば窓の位置を少し変える程度であれば、手続きが不要な場合もありますが、構造や規模、用途など、建築確認申請の際に審査を受けた内容に影響を与えるような変更の場合は、改めて確認が必要です。計画変更確認申請を怠ったまま工事を進めると、完了検査に合格できず、検査済証が交付されないといった問題が生じる可能性があります。また、法令違反となるような変更を行った場合は、是正命令が出されることもあります。計画変更が生じた場合は、速やかに建築士などの専門家に相談し、必要な手続きについて確認することが重要です。変更の内容によっては、当初の申請と同程度の時間と費用がかかる場合もあるため、計画変更はできるだけ避けることが望ましいですが、やむを得ない場合は適切な手続きを行うようにしましょう。
建築確認済証や検査済証を紛失した場合
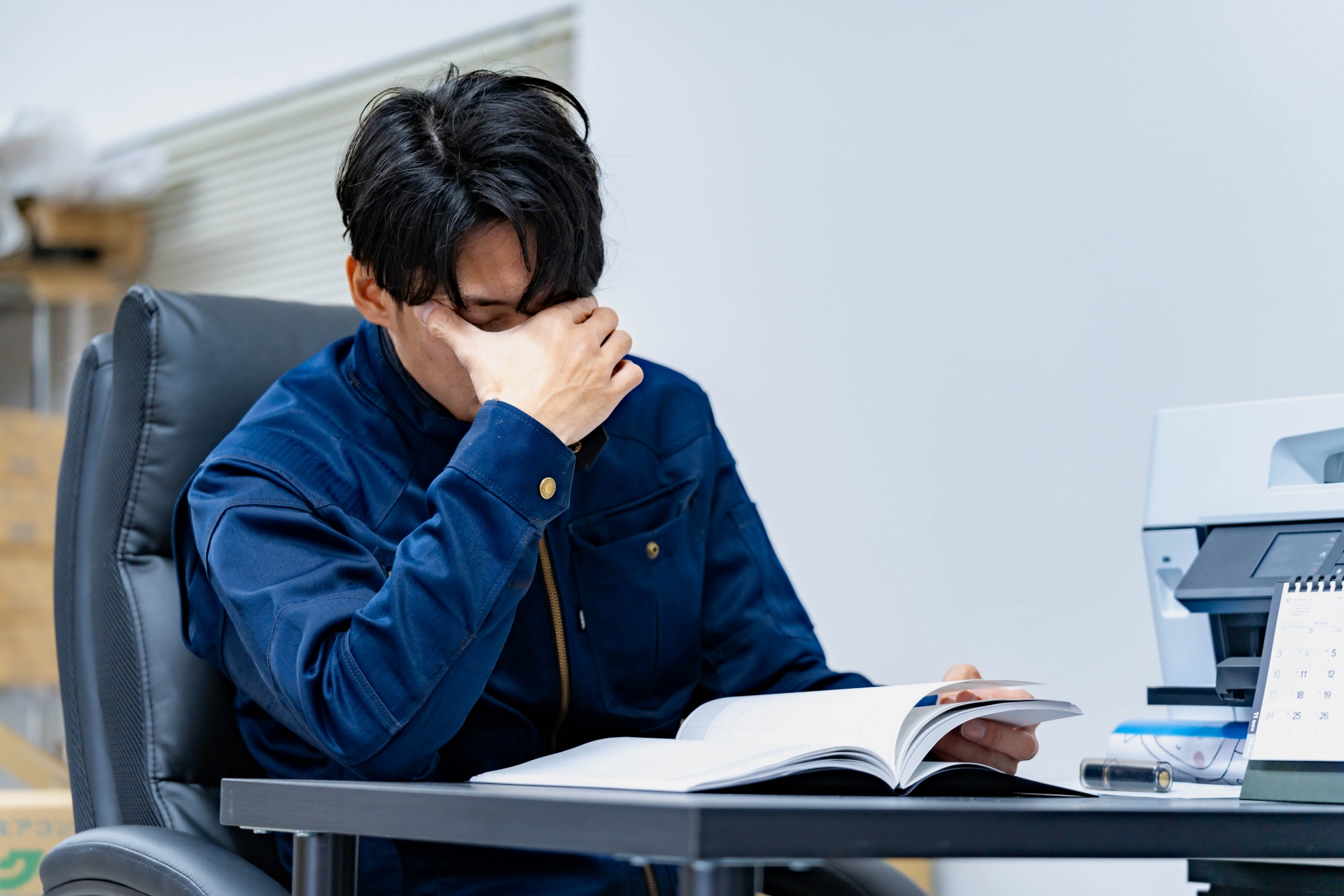
建築確認済証や検査済証は、建物の合法性を証明する重要な書類であり、将来的に建物の売却や増改築を行う際に必要となる場合があります。これらの書類を紛失してしまった場合、原則として再発行はできません。しかし、紛失した場合でも対処法は存在します。ここでは、これらの書類を紛失した場合の一般的な取り扱いと、その際の対処法について解説します。
原則再発行は不可
建築確認済証や検査済証は、一度交付された原本が非常に重要視されており、原則として再発行されることはありません。これは、これらの書類がその時点での建築計画の確認や、工事完了時の検査結果を証明するものであり、後から安易に再発行されることによって、不正な建物の流通や改変を防ぐという目的があるためです。したがって、これらの書類は、大切に保管しておく必要があります。万が一紛失してしまった場合は、再発行という形での入手は期待できないことを理解しておく必要があります。
紛失時の対処法
建築確認済証や検査済証を紛失してしまい、再発行が原則として不可能な場合でも、いくつか対処法があります。まず、建築確認申請や完了検査を行った役所(特定行政庁)に問い合わせてみることが考えられます。役所には、過去の建築確認申請に関する書類が保管されている場合があり、申請台帳の閲覧や、台帳記載事項証明書、あるいは建物の概要書の交付を受けられることがあります。これらの書類は、建築確認済証や検査済証そのものではありませんが、建築確認を受けた事実や検査に合格した事実を証明する書類として利用できる場合があります。特に、過去に建築確認や検査を受けていることが確認できれば、将来的な手続きにおいてその旨を証明するための手がかりとなります。ただし、保管期間が経過している場合や、制度が変更されている場合など、必ずしも全ての情報が得られるとは限りません。まずは、対象の建物を所管する役所の建築関連部署に相談してみるのが良いでしょう。また、建物を建築した際に依頼した建築会社や設計事務所に記録が残っている可能性もありますので、そちらにも確認してみると良いでしょう。
建築確認申請や建築トラブル

建築確認申請はスムーズに進むことが理想ですが、時には申請が通らなかったり、建築工事中に予期せぬトラブルが発生したりすることもあります。ここでは、建築確認申請が不許可となった場合の対策や、実際に起こりうる建築トラブルのケースと、その際の一般的な対応策について解説します。
申請が通らない場合の対策
建築確認申請が不許可となる主な理由は、提出された計画が建築基準法や関連法令に適合していない場合です。申請が通らなかった場合は、まず行政または指定確認検査機関から不許可となった理由が通知されますので、その内容を詳細に確認することが重要です。理由が明確になったら、建築士などの専門家と協力して、不適合な箇所を修正するなどの対策を講じます。例えば、建ぺい率や容積率の制限を超過している場合は、建物の規模を縮小する、構造耐力に問題がある場合は、構造設計を見直すといった対応が必要になります。修正後の計画で再度建築確認申請を行い、許可を得る必要があります。不許可の理由によっては、計画を大幅に見直す必要がある場合もあり、時間や費用が追加でかかる可能性も考慮に入れておく必要があります。専門家と密に連携を取り、不許可となった原因を正確に把握し、適切な対策を講じることが、無事に建築確認を得るための鍵となります。
建築トラブルのケースと対応
建築工事においては、様々なトラブルが発生する可能性があります。例えば、工事の遅延、設計内容と異なる施工、追加費用の発生、近隣住民とのトラブルなどが挙げられます。これらのトラブルが発生した場合、まずは建築会社や施工業者との話し合いによる解決を目指すのが一般的です。契約書の内容を確認し、問題点を具体的に伝え、是正や補償について協議を行います。話し合いで解決しない場合は、建築に関する専門家である建築士に相談したり、国民生活センターや各自治体の建築相談窓口に相談したりすることも有効な手段です。また、瑕疵担保責任に基づき、施工業者に対して補修や損害賠償を請求できる場合があります。より複雑な問題や損害が大きい場合は、弁護士に相談し、法的な手続きを検討する必要が出てくることもあります。建築請負契約には、万が一のトラブルに備えた条項が含まれていることが一般的ですので、契約内容を十分に理解しておくことが重要です。トラブルの例として、工事の進捗状況が契約時の予定より大幅に遅れる、使用される建材が契約書に記載されたものと異なる、あるいは基礎工事に問題が見つかるといったケースがあります。どのようなトラブルであっても、冷静に対応し、専門家のアドバイスを仰ぎながら解決に向けて進めることが大切です。
工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1
可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。
※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
人気記事
工場・倉庫建築について
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
- これから計画を始める方
- おおよその予算やスケジュールが知りたい方
- 敷地調査や提案を希望される方





