倉庫・工場のコンクリート床や塗床がひび割れる(クラック)のはなぜ?原因や補修方法、予防のための対策について

最終更新日:
倉庫や工場のコンクリート床に発生するひび割れは、見た目の問題だけでなく、建物の耐久性や安全性にも関わる重要なサインです。 この記事では、コンクリート床にひび割れ(クラック)が発生する主な原因から、危険なひび割れの見分け方、具体的な補修方法、そしてひび割れを未然に防ぐための予防策までを網羅的に解説します。
適切な知識を身につけ、資産価値と安全な作業環境を維持しましょう。
倉庫・工場のコンクリート床がひび割れするのはなぜ?

コンクリート床のひび割れは、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発生します。 コンクリートの性質に起因する乾燥収縮や温度変化によるものから、地盤沈下や過大な荷重といった外的な要因、さらには施工時の不備が原因となるケースもあります。
これらの原因を正しく理解することが、適切な補修や予防策を講じるための第一歩となります。
乾燥による収縮
コンクリートは、セメントと水が化学反応(水和反応)を起こして硬化しますが、その過程で余分な水分が蒸発します。 水分が失われるとコンクリートの体積が減少し、内部に引っ張り応力が発生します。 この応力がコンクリートの引っ張り強度を上回ったときに、表面にひび割れが生じます。
特に、コンクリートを打設した後の初期段階は水分蒸発が激しく、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすい時期です。 急激な乾燥はひび割れのリスクを高めるため、適切な養生が求められます。
気温変化による収縮
コンクリートは、温度の変化によって膨張と収縮を繰り返す性質を持っています。 外気温が低下するとコンクリートは収縮し、上昇すると膨張します。 この動きが拘束されている場合、内部に応力が蓄積され、ひび割れの原因となります。
特に、一日の寒暖差が激しい地域や、冷凍倉庫のように温度管理が厳密な施設では、温度変化による伸縮がひび割れを引き起こす要因になりやすいです。 このような動きを吸収するために、意図的に目地を設けるなどの対策が取られます。
地盤沈下による圧力
建物を支える地盤が不均一に沈下すると、コンクリート床には想定外の力が加わります。 地盤が均等に沈下すれば問題は少ないですが、部分的に沈下が進むと、床が傾いたり、たわんだりして大きな応力がかかり、ひび割れが発生します。
特に、軟弱地盤や埋立地、あるいは建物の周辺で大規模な掘削工事が行われた場合などに地盤沈下が起こりやすいです。 この場合のひび割れは、建物の構造自体に影響を及ぼす深刻な問題である可能性が高く、専門家による詳細な調査が必要です。
施工不良による強度不足
コンクリート床の強度は、設計だけでなく施工の品質に大きく左右されます。 例えば、コンクリートを練り混ぜる際の水の量が多すぎると、硬化後の強度が低下し、乾燥収縮も大きくなるため、ひび割れやすくなります。
また、コンクリートを流し込んだ後の締固めが不十分だと、内部に空隙が残ってしまい、所定の強度が得られません。 さらに、硬化過程での急激な乾燥を防ぐ養生が不適切であった場合も、初期ひび割れや強度不足の原因となり、将来的な耐久性に影響を及ぼします。
凍結融解
コンクリートの微細な隙間から侵入した水分が、冬季などに凍結することでひび割れを誘発する現象です。 水は凍ると体積が約9%膨張するため、コンクリート内部で強い圧力を発生させます。 この圧力によって内部組織が破壊され、ひび割れが生じます。 そして、気温が上昇して氷が融けると、その隙間にさらに多くの水分が侵入します。
この凍結と融解のサイクルが繰り返されることで、ひび割れは徐々に拡大し、コンクリートの劣化が進行していきます。 特に寒冷地や冷凍倉庫などで注意が必要です。
中性化
本来、コンクリートの内部は強いアルカリ性であり、その環境が内部の鉄筋を錆から守っています。 しかし、空気中の二酸化炭素がコンクリートの隙間から侵入すると、炭酸化反応を起こして徐々にアルカリ性を失い、中性に近づいていきます。 この現象が中性化です。
中性化が鉄筋の位置まで進行すると、鉄筋は錆びやすくなります。 鉄筋が錆びると体積が膨張し、その圧力で内側からコンクリートを押し広げるため、ひび割れやコンクリートの剥離を引き起こします。
過負荷
コンクリート床は、設計段階で想定された荷重に耐えられるように作られています。 しかし、その想定を超える重量の機械を設置したり、重量物を積んだフォークリフトが頻繁に通行したりすると、床に過大な負荷がかかり続けます。
この過負荷がコンクリートの許容応力を超えると、ひび割れが発生します。 特に、重量ラックの脚部や、車両の通行ルートなど、局所的に大きな力が集中する場所で起こりやすいです。 レイアウト変更や新たな設備の導入の際には、床の耐荷重を確認することが重要です。
地震によるダメージ
地震が発生すると、その揺れによって建物全体に大きな力が加わります。 床のコンクリートも例外ではなく、地盤からの突き上げるような力や、建物のねじれによって強い応力を受け、ひび割れが発生することがあります。
軽微なひび割れで済む場合もありますが、時には建物の構造的な安全性に関わる深刻なダメージにつながることもあります。 地震の後は、特に柱や壁の周りを中心に、床に新たなひび割れが発生していないか、既存のひび割れが拡大していないかを注意深く点検することが求められます。
コンクリート床のひび割れの種類

コンクリート床に発生するひび割れは、すべてが同じではありません。 その幅や深さ、原因によっていくつかの種類に分類され、危険度も異なります。 代表的なものとして、比較的緊急性の低い「ヘアクラック」と、建物の安全性に関わる可能性のある「構造クラック」があります。
これらの違いを理解することは、適切な初期対応を行う上で非常に重要です。
ヘアクラック
ヘアクラックとは、その名の通り髪の毛のように細いひび割れのことで、一般的に幅が0.3mm未満、深さが4mm未満のものを指します。 主に、コンクリート表面の乾燥収縮や温度変化などが原因で発生し、構造的な強度には直接影響を及ぼさないケースがほとんどです。
そのため、直ちに大規模な補修が必要になることは少ないですが、放置すると水分や化学物質が侵入するきっかけとなり、将来的な劣化を促進する可能性があります。 経過を観察し、数が増えたり幅が広がったりするようであれば注意が必要です。
構造クラック
構造クラックは、幅が0.3mm以上、深さが4mm以上の比較的大きなひび割れを指します。 この規模のひび割れは、コンクリートの内部にある鉄筋まで達している可能性が高いです。 原因としては、設計時の想定を超える荷重、地盤沈下、建物の構造的な欠陥、地震によるダメージなどが考えられます。
構造クラックを放置すると、ひび割れから雨水などが侵入して鉄筋を腐食させ、建物の耐力や耐久性を著しく低下させる危険性があります。 発見した場合は、速やかに専門家による診断を受け、適切な補修を行う必要があります。
補修が必要な危険なひび割れの見分け方

床にひび割れを発見した際、それが緊急に対応すべき危険なものかどうかを判断する必要があります。 すべてのひび割れが即座に問題となるわけではありませんが、中には建物の安全性に直結するサインも隠されています。
ひび割れの幅や深さ、進行状況、周辺の状態などを注意深く観察することで、補修の優先順位を見極めることができます。
ひび割れの幅が0.3mm以上、深さが4mm以上
ひび割れの幅が0.3mm、深さが4mmを超えるものは「構造クラック」に分類され、危険なひび割れと判断する一つの目安になります。 このサイズになると、ひび割れがコンクリート内部の鉄筋にまで達している可能性が高まります。
鉄筋まで水分や空気が到達すると、鉄筋の腐食が始まり、建物の構造的な強度を支える重要な要素が損なわれていきます。 コンクリートの中性化も促進され、耐久性が大幅に低下する原因となるため、専門家による診断と早急な補修が推奨されます。
ひび割れが進行・拡大している
発見当初は小さなひび割れであっても、時間の経過とともにその長さや幅が目に見えて大きくなっている場合、それは危険な兆候です。 ひび割れが進行しているということは、地盤沈下や建物の歪みなど、ひび割れを発生させている原因が今も継続していることを示唆しています。 表面的な補修だけでは解決せず、根本的な原因を特定して対策を講じなければ、補修してもすぐに再発する可能性が高いです。
定期的にひび割れの状況を記録し、変化が見られる場合は専門業者に相談しましょう。
ひび割れ周辺にズレや段差がある
ひび割れを境にして、コンクリート床の高さにズレや段差が生じている場合、これは非常に危険な状態を示しています。 この現象は、床スラブ(床版)自体が破断しているか、床下の地盤が不均等に沈下していることによって引き起こされる可能性が高いです。
単なる表面の劣化ではなく、建物の構造そのものに重大な問題が発生しているサインであり、放置すれば床の陥没や、さらなる構造的ダメージにつながる恐れがあります。 このようなひび割れを発見した際は、直ちに専門家による緊急の点検が必要です。
倉庫・工場のクリート床がひび割れたときの補修方法

コンクリート床のひび割れを補修する工法は、ひび割れの幅や深さ、原因、そして求められる機能(強度回復、防水など)によって多岐にわたります。 ひび割れの内部に樹脂を注入する方法や、表面をコーティングする方法、ひび割れをカットして充填する方法など、それぞれの状況に適した工法を選択することが、確実な補修効果を得るために重要です。
注入工法
注入工法は、ひび割れ部分にドリルで穴を開け、そこから専用の器具を使ってエポキシ樹脂などの低粘度で接着性に優れた補修材を圧入する手法です。 ひび割れの末端まで樹脂を充填させることで、コンクリートを一体化させ、構造的な強度を回復させます。 また、ひび割れを塞ぐことで、水や劣化要因の侵入経路を遮断する効果も期待できます。
特に、建物の構造耐力に関わるような比較的幅の広い「構造クラック」の補修に適しており、ひび割れ自体の強度を取り戻したい場合に有効な工法です。
被覆工法
被覆工法は、ひび割れが生じているコンクリート表面を、防水性や耐久性のある塗膜材、シート状の材料、あるいは左官材などで覆い隠す補修方法です。 この工法は、ひび割れそのものを物理的に接着・固定するのではなく、表面を保護することで外部からの水や二酸化炭素などの劣化因子の侵入を防ぐことを主な目的とします。
比較的軽微なヘアクラックが広範囲に多数発生している場合や、床全体の防水性能を高めたい場合に適しています。 ひび割れの動きに追従できる弾性のある材料を選ぶこともあります。
充てん工法
充てん工法は、まずひび割れに沿って電動カッターなどでU字型またはV字型に溝(目地)を設けます。 次に、その溝の中を清掃し、プライマーを塗布した後、シーリング材や樹脂モルタルなどの補修材を充填する手法です。 この工法は、比較的動きの大きいひび割れ(ワーキングクラック)の補修に適しており、充填材の柔軟性によってコンクリートの伸縮にある程度追従できます。
ひび割れの再発を抑制し、水密性を確保する目的で用いられることが多く、注入工法と組み合わせて施工されることもあります。
オーバーレイ
オーバーレイ工法は、既存のコンクリート床の表面を清掃・下地処理した上で、その上から新しいコンクリートやモルタル、ポリマーセメントなどを数センチ程度の厚みで打設し、床全体を一体的にリニューアルする手法です。 ひび割れだけでなく、摩耗や凹凸など床全体の劣化が著しい場合に採用されます。 床の耐久性や平滑性を大幅に向上させることができ、耐荷重性能を高めることも可能です。
オーバーレイ工法は、既存の舗装の上に新しい舗装を重ねるため、切削作業などが不要で、他の工法に比べて工事期間が短く、コストも抑えられる傾向があります。 大規模な改修が必要な場合に検討される工法です。
ポリマーセメントモルタルの補修
ポリマーセメントモルタルは、通常のセメントモルタルにアクリル系やゴム系のポリマーを混入した補修材料です。 ポリマーを添加することにより、通常のモルタルに比べてコンクリートとの接着性、防水性、曲げ強度、耐摩耗性などが大幅に向上します。 この材料を用いて、ひび割れやコンクリートの欠損部を埋めたり、断面を修復したりします。
コンクリートとの馴染みが良く、一体化しやすいため、小規模な欠けから比較的大きな断面修復まで、幅広い補修に用いられる汎用性の高い工法です。
含浸工法
含浸工法は、けい酸塩系の液体状の含浸材をコンクリート表面に塗布または噴霧する手法です。 塗布された含浸材はコンクリート内部に深く浸透し、セメントの水和反応で生成された物質と化学反応を起こして、緻密で水を通しにくい結晶体を形成します。
これにより、コンクリート自体の組織を改質し、強度や水密性を向上させます。 ひび割れを直接埋めるのではなく、コンクリート自体を強化することで劣化の進行を抑制し、新たなひび割れの発生を防ぐ効果が期待できるため、予防保全や初期段階の対策として有効です。
コンクリート床のひび割れを補修する際の注意点

コンクリート床のひび割れ補修を効果的に行うためには、いくつかの重要な注意点があります。 最も大切なのは、ひび割れが発生した根本的な原因を正確に突き止めることです。 原因を特定しないまま表面的な補修を行っても、問題が再発する可能性が高くなります。 例えば、地盤沈下が原因であれば、床の補修だけでなく地盤改良が必要になるかもしれません。
また、ひび割れの状況に応じて最適な工法と材料を選定することも重要です。 補修前には、補修箇所の汚れや脆弱な部分を完全に取り除くなど、丁寧な下地処理を行うことが、補修材の密着性を高め、長期的な効果を維持するために不可欠です。
DIYでの補修は可能?業者に依頼すべきケース

コンクリート床のひび割れを発見した際、市販の補修材を使って自分で対応できるのか、それとも専門業者に依頼すべきか迷うことがあります。 ひび割れの規模や種類によってはDIYでの補修も可能ですが、建物の安全性に関わるケースも少なくありません。
誤った対応は問題を悪化させる可能性もあるため、DIYで対応できる範囲と、専門的な判断が必要なケースを正しく見極めることが重要です。
DIYで補修できるひび割れ
DIYでの補修が可能なのは、主に幅0.3mm未満の「ヘアクラック」のような、構造上の強度に直接影響しない軽微なひび割れに限られます。 ホームセンターなどで入手できるひび割れ補修用のセメントスプレーや、シーリング材、パテなどをひび割れに充填する方法が一般的です。
これらの作業は、主にひび割れからの水分の侵入を防ぎ、見た目を改善するための応急処置的な意味合いが強いです。 作業前には、ワイヤーブラシなどで補修箇所の清掃を十分に行うことが、補修材を密着させるために重要になります。
専門業者に依頼すべきひび割れ
幅が0.3mm以上の「構造クラック」や、時間とともにひび割れが拡大している場合、ひび割れ部分に段差が生じている場合は、建物の安全性に関わる問題が潜んでいる可能性があるため、必ず専門業者に相談すべきです。 これらのひび割れは、地盤沈下や設計上の問題、鉄筋の腐食など、専門的な知識がなければ原因の特定が困難です。
自己判断で補修を行うと、根本的な原因を見過ごし、かえって状況を悪化させる危険性があります。 専門業者であれば、適切な診断に基づき、原因に応じた最適な工法で確実な補修を行ってくれます。
コンクリート床のひび割れ補修にかかる費用相場
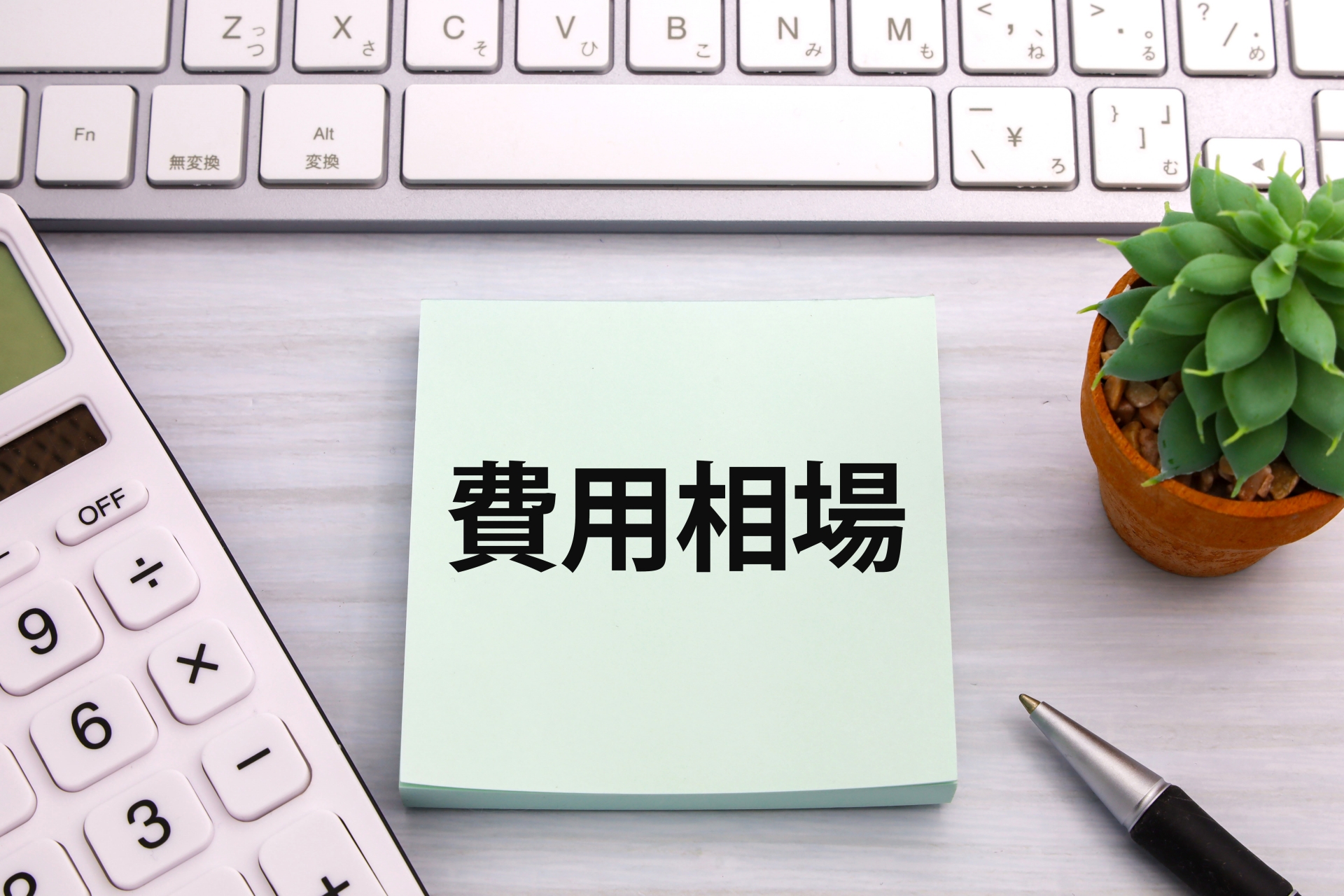
コンクリート床のひび割れ補修にかかる費用は、DIYで行うか、専門業者に依頼するかで大きく異なります。 また、業者に依頼する場合でも、ひび割れの規模や深さ、採用する工法によって費用は大きく変動します。
ここでは、それぞれのケースにおける費用の目安を解説しますが、正確な金額を知るためには、必ず業者から見積もりを取ることが必要です。
DIYで補修する場合の費用
DIYで軽微なヘアクラックなどを補修する場合、費用は主に材料費のみとなります。 ひび割れ補修用のセメントスプレーやカートリッジ式のシーリング材、補修用パテなどは、それぞれ1,000円から数千円程度で購入できます。
これに加えて、補修箇所を清掃するためのワイヤーブラシや、作業をきれいに行うためのヘラ、マスキングテープなどの道具を揃える費用も考慮する必要があります。 小範囲の補修であれば、総額で数千円から1万円程度の予算で収まることが多いでしょう。
業者に依頼する場合の費用
専門業者に依頼する場合の費用は、工法や施工範囲によって大きく変わります。 比較的簡易なエポキシ樹脂の注入工法やUカット充てん工法では、ひび割れの長さ1メートルあたり数千円から1万5千円程度が目安となります。 ただし、これには最低施工料金が設定されている場合も多いです。
劣化が広範囲に及び、床全体を補強するオーバーレイ工法などを採用する場合は、1平方メートルあたり1万円から数万円の単価となり、施工面積によっては総額で数十万円から数百万円に及ぶこともあります。 まずは複数の業者から詳細な見積もりを取り、費用と工法を比較検討することが重要です。
信頼できる補修業者の選び方

適切なひび割れ補修を行うためには、信頼できる専門業者を選ぶことが極めて重要です。 まず、コンクリート診断士や施工管理技士といった専門的な資格を持つ技術者が在籍しているかを確認しましょう。 資格は、一定の知識と技術力を持つ証となります。
また、倉庫や工場など、類似の建物の床補修における施工実績が豊富かどうかも重要な判断材料です。 過去の事例を見せてもらうことで、その業者の得意分野や技術レベルを把握できます。 さらに、ひび割れの原因をしっかりと調査し、その結果に基づいて複数の工法を提案してくれる業者であるかどうかも見極めるポイントです。 見積もりの内訳が明確で、アフターフォローや保証についてもきちんと説明してくれる誠実な業者を選ぶことが大切です。
倉庫・工場のコンクリート床のひび割れ防止対策

コンクリート床のひび割れは、発生後の補修も重要ですが、設計や施工の段階から予防策を講じることが、建物の長寿命化と長期的なコスト削減につながります。
また、建物が完成した後も、適切な運用とメンテナンスを継続することで、ひび割れの発生リスクを低減させることが可能です。ここでは、ひび割れを未然に防ぐための具体的な対策を紹介します。
床の材料の配合を工夫する
ひび割れを防ぐための対策は、コンクリートの材料配合から始まります。 例えば、コンクリートの乾燥収縮を抑制する効果のある「収縮低減剤」をあらかじめ混入する方法があります。 また、ポリプロピレンなどの短い繊維(ファイバー)をコンクリートに混ぜ込むことで、微細なひび割れの発生を抑制し、分散させる効果が期待できます。
建物の用途や立地環境、求められる床の性能に応じて、こうした特殊な混和剤や材料を適切に選定・配合することが、ひび割れに強いコンクリート床を実現するための重要な要素となります。
施行後に処置を行う
コンクリート打設後の初期養生は、ひび割れ防止において非常に重要な工程です。 コンクリート表面が急激に乾燥すると、大きな収縮ひび割れが発生しやすくなります。 これを防ぐため、散水や養生マットでコンクリート表面を一定期間湿潤状態に保つ「湿潤養生」を徹底することが求められます。
また、コンクリートが収縮する際に発生する応力を計画的に逃がすため、一定間隔でカッターを用いて目地(収縮目地)を設けることも極めて有効な対策です。 これにより、不規則なひび割れの発生を抑制し、目地の部分にひび割れを誘導できます。
定期的にメンテナンスを行う
建物が完成し、運用が開始された後も、ひび割れ防止の対策は続きます。 床面を定期的に点検し、ごく初期の軽微なひび割れ(ヘアクラック)を発見した段階で、表面保護材や含浸系の劣化防止材を塗布するなどの予防保全を行うことが効果的です。
これにより、ひび割れからの水分の侵入を防ぎ、劣化の進行を遅らせることができます。 また、床面の清掃をこまめに行い、油や化学薬品が付着したまま放置しないことも、コンクリートの劣化を防ぎ、健全な状態を長く保つために重要です。
再振動締固め
再振動締固めは、コンクリート打設時の施工技術の一つで、ひび割れ防止に効果的な手法です。 これは、一度締固めを行ったコンクリートが硬化を開始する前の適切なタイミングで、再度バイブレーターなどを用いて振動を与える作業です。
この再振動により、コンクリート内部のブリーディング水(沈降した骨材から分離した余剰水)や閉じ込められた空気を排出し、コンクリートの組織をより緻密にすることができます。 結果として、コンクリートの沈降に伴うひび割れ(沈みひび割れ)の発生を抑制し、強度や水密性の向上にもつながります。
倉庫・工場のクリート床のひび割れを放置するリスク

コンクリート床のひび割れは、単なる見た目の問題ではありません。 一見すると些細なひび割れでも、それを放置することで様々なリスクが生じ、最終的には建物の安全性や企業の事業継続にまで影響を及ぼす可能性があります。
ひび割れがもたらす潜在的な危険性を理解し、早期に対応することの重要性を認識する必要があります。
ひび割れの拡大
最初に発生した小さなひび割れを放置すると、多くの場合、そのひび割れは徐々に進行・拡大していきます。 フォークリフトなどの車両通行による振動や衝撃、日々の温度変化によるコンクリートの伸縮、あるいはひび割れから侵入した水分による劣化などが、ひび割れをさらに大きくする原因となります。
最初は補修が容易だったヘアクラックも、時間とともに深刻な構造クラックへと発展する可能性があります。 ひび割れが大きくなるほど、補修工事は大規模になり、それに伴って費用も高額になってしまいます。
建物の劣化・強度低下
ひび割れは、コンクリート内部へ水分や空気、二酸化炭素、塩化物イオンなどを侵入させる入り口となります。 これらの物質が内部の鉄筋に達すると、鉄筋の腐食が始まります。 鉄筋が錆びると体積が膨張し、内側からコンクリートを破壊する「爆裂」という現象を引き起こすこともあります。
鉄筋の腐食や爆裂は、コンクリートと鉄筋の一体性を損ない、建物の構造体としての強度を著しく低下させます。 この状態を放置すると、建物の耐震性や耐久性が損なわれ、安全性に深刻な問題が生じます。
作業効率の低下・事故の危険性
倉庫や工場において、床の健全性は作業の安全性と効率に直結します。 ひび割れや、それが原因で生じた段差は、フォークリフトや台車のスムーズな走行を妨げます。 走行時の振動で運搬中の荷物が崩れたり、車両のタイヤや車体にダメージを与えたりする原因となります。
さらに深刻なのは、作業員が段差につまずいて転倒し、怪我をするなどの労働災害につながる危険性です。 安全で効率的な作業環境を維持するためには、床面を常に平滑で良好な状態に保つことが不可欠です。
構造的な問題・建物の倒壊
特に構造クラックを長期間にわたって放置した場合、建物の安全性は極めて危険な状態に陥ります。 鉄筋の腐食やコンクリートの劣化が進行し、建物の強度が著しく低下した状態で、大規模な地震などの強い外力が加わると、床が抜け落ちたり、柱や梁が損傷したりする可能性があります。
最悪のケースでは、建物全体の倒壊につながる危険性も否定できません。 ひび割れは、建物の構造が発する危険信号である場合があることを認識し、決して軽視することなく、専門家による適切な診断と対策を講じる必要があります。
よくある質問

倉庫や工場のコンクリート床のひび割れに関して、管理者や担当者の方々から多く寄せられる質問があります。 ここでは、特に質問の多い事項について、具体的な回答をまとめました。
日々の管理や、いざという時の対応の参考にしてください。
軽いひび割れ(ヘアクラック)なら放置しても大丈夫ですか?
幅0.3mm未満のヘアクラックは、直ちに建物の構造的な強度に影響を及ぼす可能性は低いです。 しかし、完全に放置することは推奨されません。 なぜなら、どんなに小さなひび割れでも、そこから水分や二酸化炭素が侵入する可能性があるからです。 これらの侵入は、コンクリートの中性化を促進したり、内部鉄筋の腐食につながる第一歩となったりします。
そのため、経過を注意深く観察し、数が増えたり、幅が広がったりするような変化がないかを確認することが重要です。 予防的な措置として、表面に保護塗料を塗布するなどの簡単なメンテナンスをしておくと、劣化の進行を効果的に抑制できます。
コンクリート床のひび割れ補修にはどのくらいの時間がかかりますか?
補修に必要な時間は、ひび割れの程度、範囲、そして採用する工法によって大きく異なります。 数メートル程度のひび割れに対して、エポキシ樹脂注入工法やUカット充てん工法で補修する場合、下準備から施工完了まで1日以内で終わるケースも多くあります。
しかし、補修範囲が広範囲にわたる場合や、床全体を新たに打ち直すオーバーレイ工法などを採用する場合は、下地処理やコンクリートの養生期間が必要となるため、数日から数週間の工期を要することもあります。 工場の稼働を止めなければならない場合もあるため、事前に業者と工程や工期について綿密な打ち合わせが必要です。
賃貸の倉庫・工場でひび割れを見つけたらどうすればいいですか?
賃貸物件の床にひび割れを発見した場合、勝手にDIYで補修したり、業者を手配したりする前に、まずは建物の所有者であるオーナーや管理会社に速やかに連絡することが最優先です。 ひび割れは建物の構造に関わる重要な問題である可能性があり、補修の責任の所在や費用負担については、賃貸借契約書の内容に基づいて判断されます。
一般的に、経年劣化によるひび割れは貸主(オーナー)の責任で修繕し、テナント側の使用方法(過積載など)に起因する損傷は借主の責任となることが多いです。 まずは状況を正確に報告し、その後の対応について指示を仰ぐのが正しい手順です。
まとめ
倉庫や工場のコンクリート床に発生するひび割れは、乾燥収縮といった自然な現象から、地盤沈下や過大な荷重といった構造に関わる深刻な問題まで、多岐にわたる原因によって引き起こされます。 ひび割れは「ヘアクラック」と「構造クラック」に大別され、特に幅0.3mm以上のひび割れや進行が見られるものは、建物の安全性に影響を及ぼす危険なサインです。
補修にあたっては、原因を正確に特定し、注入工法や充てん工法など、状況に応じた適切な工法を選ぶ必要があります。 ひび割れを放置すると、建物の劣化、事故の誘発、最悪の場合は構造的な問題へと発展するリスクがあるため、定期的な点検と早期の対応が、建物の資産価値と安全な作業環境を守る上で不可欠です。
工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1
可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。
※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。
※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください
SAWAMURAについて
1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に
さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。
豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。
積み重ねた施工実績とノウハウで、
確かな精度を保証します。
- 2020年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位
- 2019年
- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位
関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞
アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年
- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞
アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2016年
- アクティブビルダー銅賞受賞
- 2015年
- アクティブビルダー 銅賞受賞
- 2012年
- 連続販売年数15年達成
- 2013年
- 15年連続受注賞
- 2008年
- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞
- 2004年
- 優秀ビルディング
資格所有者
-
一級建築士 13人
二級建築士 41人
一級建築施工管理技士 29人
一級土木施工管理技士 10人 -
宅地建物取引士 19人
設備設計一級建築士 1人
土地家屋調査士 1人
一級建設業経理士 2人
中小企業診断士 1人
会社概要
| 社名 | 株式会社澤村 |
|---|---|
| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |
| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |
| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |
| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |
| 創業 | 昭和25年12月6日 |
| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |
| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |
| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |
| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |
| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |
| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |
人気記事
工場・倉庫建築について
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
- これから計画を始める方
- おおよその予算やスケジュールが知りたい方
- 敷地調査や提案を希望される方





